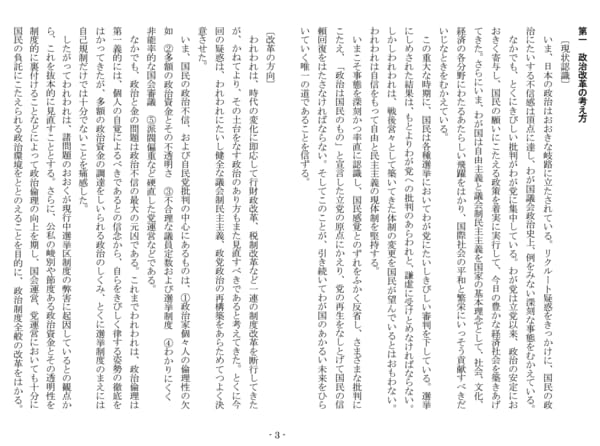繰り返す「ルール作り」とルール破り
読者のなかには、ルールを作ってそれを守れば、政治の課題の1つである「お金の問題」は解決する、そう思う方もいるかもしれません。
ところが、自民党は約30年前にも同じことをやっています。1980〜90年代にかけても、政治と金の問題が相次ぎました。ロッキード事件、リクルート事件、東京佐川急便事件などです。
特に1988年のリクルート事件のあとに、自民党内でも「これではいかん」という声が高まりました。そこで政府と自民党と総理の私的諮問会議で、政治と金の問題を検討しました。
その際、自民党から出てきたのが「政治改革大綱」というルールです。政治学者の佐々木毅氏(当時東京大学法学部教授)をリーダーに相当力を入れて検討されたものです。
「政治改革大綱」はいまでもインターネット上で読むことができます。
読んでいただくと明らかですが、脱派閥、政治と金の透明化など、いま議論しているのと同じようなことが書いてあります。
少し説明すると、たとえばパーティ券問題でも悪い意味で注目を集めている派閥というものは、前近代的なもので、こんなものが残っている限り自民党は近代政党になれない。だからこれはやめていくべきだ。でもすぐには難しいから段階的にやめていかなければならない。こういったことを党議決定しています。
つまり、令和のパーティ券問題は少なくとも2周目なんですね。そしてまた同じように自民党のルールを定めると言っていますが、それでいいのかという疑問が残ります。
そのほか、今回は政治資金規正法の厳格化や、領収書添付(パーティ券購入者の公開基準額)を現行の20万円超から5万円超に引き下げるという提案が公明党から出ています。しかし、そもそもすべての支出に対して領収書添付を義務づけなくていいのかという疑念も残ることでしょう。
(続きを以下のリンクからお読みください)
■連載:日本の「政治」大丈夫なんですか?
(1)【西田亮介が語る】令和の「パーティー券」裏金事件、なぜ過去の「政治とカネ」問題より悪質なのか←いまココ
(2)【西田亮介が語る】なぜ、裏金問題は繰り返されるのか?政治家が資金の使途を絶対に明らかにしたくない理由
(3)【安田洋祐が語る】なぜ、裏金問題では関係者で死者が出るのか? 「悪事を一切認めない」が招く最悪の結末
(4)【安田洋祐が語る】ダイハツの認証不正と政治家の裏金問題の共通点とは?政治にも「内部告発制度」が必要か