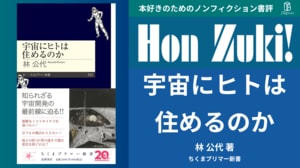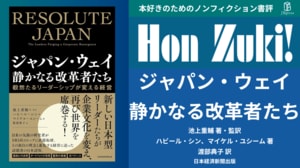筆者の吉井理人氏は、2023年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)日本代表の投手コーチとして世界一に貢献した(写真:CTK Photo/アフロ)
筆者の吉井理人氏は、2023年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)日本代表の投手コーチとして世界一に貢献した(写真:CTK Photo/アフロ)
投手コーチとして、2023年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で日本を世界一に、監督としても千葉ロッテマリーンズをクライマックスシリーズへ導いた吉井理人監督。「対話によって選手に気づきを与え、『自主性』を育てる」という指導方針は、ほかの分野でも求められるマネジメント技術だろう。自著『聴く監督』(KADOKAWA)では、その根幹を支える「傾聴法」や指導者としての振る舞いについて、野球界の裏話を交えて伝えている。野球ファンだけでなく、部下を持つ全ての社会人にとって一読の価値がある書ではないだろうか。
(東野 望:フリーライター)
「監督がいる」と意識されないように馴染む
「プロ野球の監督」と聞くと、どのようなイメージが湧くだろうか。「戦国時代の武将」のようにどーんとベンチに座り、泰然自若としているイメージを持つ方もいるだろう。しかし、本書を著した吉井監督はそんなトラディショナルな監督像とはかけ離れている。
なるべく選手との間に壁を作らないように努めるという吉井監督。用事がないときは監督室を飛び出し、選手たちのロッカールームや食堂、トレーナールーム、ウエイトトレーニング場などでともに時間を過ごし、時にはともにトレーニングもする。
選手たちに「監督がいるぞ」と意識されないくらい、自然に馴染む努力をしたという。また、選手たちの居心地が悪くならないよう、なるべく選手の前で剥き出しの感情を吐露しないようにもしていた。それらは、選手たちが気兼ねなく話せる場をつくり、選手との対話をスムーズにするためだ。
振り返りの重要性とそれを導く「対話」
吉井監督は「振り返り」こそが自分を成長へ導いてくれる最も重要なツールと考えている。反省とはネガティブなものではなく、人が成長するのに必要な養分という考え方だ。そして、選手の振り返りを導くのが吉井監督の傾聴術である「対話」だ。
そもそも吉井監督の対話とは、一般的な「対話」という言葉が持つイメージとは少しニュアンスが異なるかもしれない。それについて以下のように述べている。
対話と言っても双方向で対等のコミュニケーションを行うわけではなく、あくまでこちらは選手が言葉を発するきっかけをつくるだけだ。こちらが期待する答えに誘導するような言葉を投げかけてはいけないし、彼らが言葉を発し始めたら、後はできるだけ聞き役に徹する。
それを繰り返すことで、今自分が何を考えているのかに気づかせるとともに、どのように考え方が変化しているのかを認識させる目的がある。
監督自身が答えを与えるのではなく、あくまで選手の中にある答えを探す手伝いをするというスタンスだ。「教えないコーチング」と言われるゆえんはここにある。