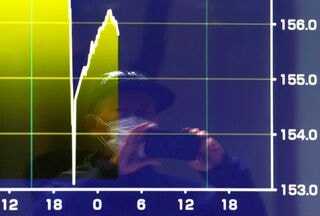継続する円安基調に日銀に対する批判も。写真は参院財政金融委員会に出席した植田和男総裁(写真:つのだよしお/アフロ)
継続する円安基調に日銀に対する批判も。写真は参院財政金融委員会に出席した植田和男総裁(写真:つのだよしお/アフロ)
円安による物価上昇懸念が深まっている。為替相場が円安傾向を強める理由として日米の金利差が指摘される中、日本銀行が4月の金融政策決定会合で前月の政策を維持したこともあり、基調は反転していない。植田和男総裁に対する批判も出ているが、日銀にとりうる手はあるのか。元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説する。(JBpress編集部)
(神津 多可思:日本証券アナリスト協会専務理事)
法律上、為替レートは財務省の所管だが…
円安が進んだ。そもそも、それが行き過ぎかどうか、いろいろな見方がある。しかし、世の中で上がっている声からは、「さすがにこのままにしておいてはいけないのではないか」という見方が増えてきたことは言えるように思う。
だからこそ、財務省は日本単独での介入を意思決定し、日本銀行が外国為替市場に介入した。とはいえ、それだけではなかなか底流にある円安圧力は衰えない。そこで、為替レートに影響を与え得る金融政策についても、「さすがにこのままではいけない」という判断と平仄が合ったものにすべきだとの声も出ている。
法律上は、為替レートのことは財務省の所管となっているが、日本銀行は日本経済の健全なる発展を理念としている。このところの円安がその理念に背いているなら「為替レートのことは関係ない」とは言えないだろう。
そもそも為替レートはどう決まるか
円安が行き過ぎかどうかを考えるためには、為替レートがどう決まるかについて整理しておいた方が良い。統計学や計量経済学を駆使しても、為替レートの振る舞いは結局のところ「ランダム・ウォーク」、すなわち明日のことは分からないという結論になってしまう。
それでも理屈から攻めれば、少し長い目でみた場合、次の3つの要因が影響していると言われてきた。
ひとつは「相手国とのインフレ率の差」である。米ドルについて言えば、米国と日本のインフレ率を対比し、低い方の通貨に切り上げ圧力が加わる。詳細は省くが、いわゆる購買力平価の考え方である。
つい先頃までは、日本は米国より低インフレであったので、この観点からは常に円高圧力が生じていた。