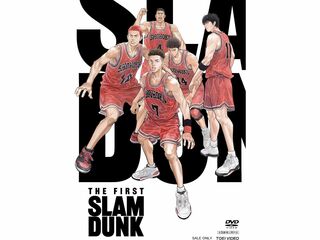幸せはいつもそこにある
いろいろな幸せのかたちはあると思うが、わたしの幸せに対する考えは決まっている。
司馬遼太郎の『台湾紀行 街道をゆく 40』(朝日文庫)のなかに、わたしの考える幸せにぴったりな文章がある。これを読んだだけで、一日幸せになれる文章である。
夕方、六歳の準ちゃんは、自宅の裏のガジュマルの樹にのぼった。
枝葉の茂みが、ソファのようにやわらかい。
いつもとちがって屋根の瓦の波が目の前にあり、べつな宇宙にきたみたいだった。本を読みはじめた。
やがてお母さんが勝手口から出てきた。髪をひっつめ(ひっつめ、に傍点)にして、青っぽい和服を着ている。
「準ちゃん」
と、樹の下で、彼女は遠くにむかって呼ばわった。が、当の準ちゃんは、頭の上の樹の梢にいる。
「ごはんよ、準ちゃん」
お母さんが途方に暮れたまま、
「準ちゃんは、どこへ行っちゃったのかしら」
と、つぶやく。当の準ちゃんは、笑いをこらえて樹の上にいる。
(「魂魄」『台湾紀行 街道をゆく 40』)
これだけのことである。

「準ちゃん」こと田中準造氏は、台湾の新営という町で生まれ育った。敗戦で、六年生のときに台湾を離れ、鹿児島に移り住んだ。のち、新聞記者になり、結婚した。数年前に定年になった。
田中準造氏は、この光景を「思い出すたびに涙がこぼれる」。「涙が出ているあいだだけ、この情景のなかに浸(ひた)っていられる」からである。定年を過ぎた年になっても、「準ちゃん」はいつもこの幸せな情景とともにある。
かれは「ひとには優しく、後輩にも丁寧な言葉づかいで接し、つねに譲って我を出さない」。「おだやかな生活人で、唯一の趣味は、自分の奥さんを笑わせることである」
ほんとうの人間、ほんとうの幸せは、この母と準ちゃんみたいな関係にある。
作意も作為もない普通の人間がいい。このような記憶があることが最大の幸せである。日々、幸せな人は幸いである。
しかしそうではない多くの人も、思い出せば、幸せはいつもそこにある。
人生の目的としての幸せを求めている人は、いつまでたっても幸せが手に入らない。それはそうだ。手に入ってもこれが幸せなのか? と自信がなく、いやこれこそが幸せだと思っても、すぐ消えてしまうからだ。
だからアメリカ人みたいに、身近なところで幸せを探すようになる。もう、あるかないかの、ほんとうの幸せなんか待っていられないのだ。
かくしてパンケーキを食べて幸せになり、回転寿司をつまんで幸せになる。しかし食べ終わると終わる。けれど、もうそれでいいらしいのだ。幸せとはいまや、うれしいとか楽しいと同義なのである。
日常のこの軽い幸せは、いつまでも「ほんとうの幸せとはなにか」という幻想に呪縛されつづけるよりは、いいことかもしれない。