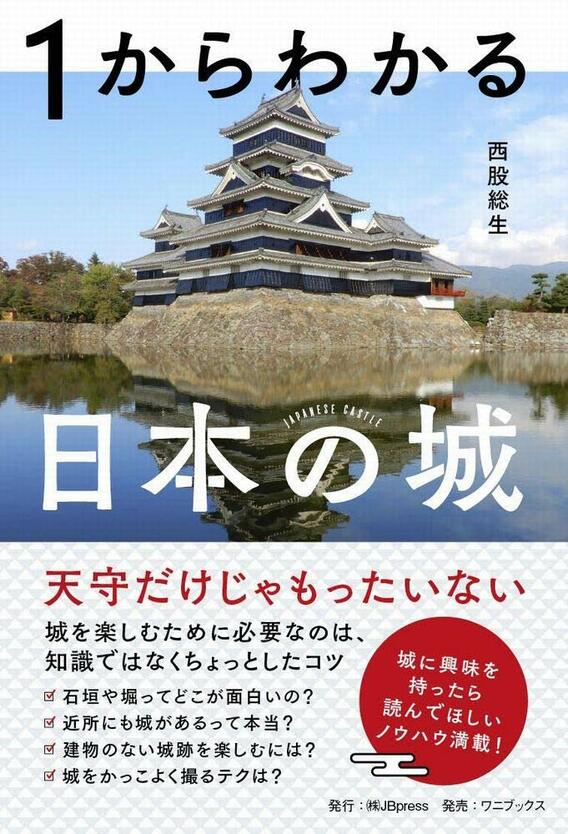撮影/西股 総生
撮影/西股 総生
(歴史ライター:西股 総生)
芥川が古典を題材にとった「王朝もの」
珠玉の小説を残した大正時代の作家、芥川龍之介(1892〜1927)の作品の中に、「王朝もの」と呼ばれる一群の短編小説がある。
これらは、『今昔物語集』や『宇治拾遺物語集』といった古典を題材にとった小説だ。代表作の『羅生門』や『鼻』は、中学・高校の国語の教科書で読んだ記憶のある方も多いだろうし、『羅生門』と『藪の中』を基にした黒澤明の映画『羅生門』を想起される方も、少なくないものと思う。
「王朝もの」という呼び名からわかるとおり、多くの作品が描くのは、平安時代の人々である。貴族や僧侶を主人公とした作品もあるが、下級官人や庶民、はては盗賊までもが生き生きと描かれる。今年の大河ドラマ『光る君へ』で、まひろの周囲にいるような人たち、というわけだ。
 芥川龍之介(1920年代) 写真/アフロ
芥川龍之介(1920年代) 写真/アフロ
芥川が、『今昔物語集』や『宇治拾遺物語集』に題材を求めたのは、明白なフィクションによって、人間のリアルな生き様を描くためである。彼が小説家を志した明治末期から大正時代にかけては、文壇の主流であった自然主義文学が私小説へと沈潜してゆく時代であったから、そうした流れに対するアンチテーゼとして、千年近くも昔の日本に舞台を求めたのだろう。
考えてみれば、大河ドラマも歴史再現ドラマではなく、歴史に題材を求めつつ、人間の生き様を現代人の求める手法で描く、フィクションである。だとしたら、『光る君へ』の参考図書として、芥川の「王朝もの」を読んでみるのも悪くない。
 平安時代には雅な貴族文化が栄える一方で… 撮影/西股 総生
平安時代には雅な貴族文化が栄える一方で… 撮影/西股 総生
たとえば、『偸盗』の登場人物達は『光る君へ』の直秀や散楽師たちを思わせる。また、『光る君へ』の今後の展開では、まひろの夫が国司として越前に赴任し、まひろも同道するはずだが、芥川の『芋粥』では、主人公の五位が藤原利仁とともに越前国府に行く話が出てくる。『芋粥』は、平安中期の都と地方社会との対比をイメージできる話である。
何より、芥川の「王朝もの」を読んでいて感じるのは、描かれている作中人物の心理や葛藤が、きわめて現代的であることだ。たとえば、代表作『鼻』で描かれているのは、容姿コンプレックスである。容姿にコンプレックスを持つ人が、問題箇所を整形したとして、はたして幸せになれるだろうか。
 羅生門跡 写真/ogurisu/イメージマート
羅生門跡 写真/ogurisu/イメージマート
『芋粥』は従来、勝ち組と負け組の対比として語られてきた。けれども、この作品で描かれているのは、ずはり蛙化現象である。作品の前半で描かれる陰湿なイジメの有り様も、現代社会に通じるものだ。
もちろん芥川は、『今昔物語集』や『宇治拾遺物語集』をそのまま現代語に訳しているわけではなく、近代的な文芸作品として翻案し、小説として再構成している。でも、だからこそ、気付くのだ。人間が抱える「生きづらさ」の本質は、平安時代も大正時代も、令和の時代も意外なほど変わっていないのだ、と。
われわれが、「現代人特有の病理」と考えがちな問題のほとんどは、実は昔からずっと人々が抱え続けてきた問題に他ならない。それを「現代人特有」と捉えてしまうこと自体が、現代人の思い上がりでしかないのである。
 岩波文庫と新潮文庫の「王朝もの」 撮影/西股 総生
岩波文庫と新潮文庫の「王朝もの」 撮影/西股 総生
そんな芥川龍之介の「王朝もの」、改めて大人の読書として味わってみてはいかがだろう。なお、芥川の作品は各社から刊行されているが、岩波文庫や新潮文庫は「王朝もの」のくくりでまとめられていて、手にしやすい。