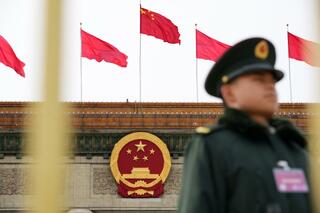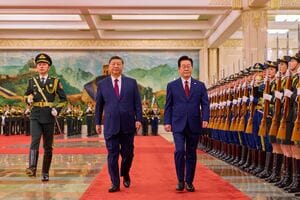ただし、これは食品とはみなされていなかった。「養老品」とあるように「くすり」の扱いだった。井伊家から将軍家へも「薬」として献上されていたのだ。滋養強壮剤としての牛肉。大石内蔵助も、討ち入り当時の最年少で、まだ10代の少年だった息子の主税に食べさせたら、かえって「悪しかるべし」と笑ってみせている。
「紅葉」や「牡丹」の隠語を使って肉食を楽しむ
そんなにカラダに良い「薬」ならば、食べても致し方ない。そんな風習も18世紀の後半になると、もっと露骨になっていく。安永年間に江戸の麹町平河町に「山奥屋」という店があった。ここに通う武家たちは「紅葉」や「牡丹」という料理を食べていた。花札の絵柄の抱き合わせや語呂合わせから、鹿や猪のことを洒落や隠語でそう呼んでいたのだ。これを「薬喰(くすりぐい)」といって、嗜んでいた。
もっとも、仏教信奉が浸透していた江戸時代にあって、食肉を厭う大名も少なくなかった。参勤交代でも、街道沿いの「山くじら」「ももんじ屋」の看板の前を極力避けて通った。「山くじら」は猪のこと、「ももんじ屋」は、猪や鹿、それに猿の肉を出す店のことだった。薬喰は猿まで食べていたというから、もっと驚く。
それでも、どうしても「ももんじ屋」の前を通らなければならないとなると、大名は駕籠を宙に高く差し上げて通り過ぎたという。それほど不浄とされていた。
それが、四つ足動物はお前の親の生まれかわりかもしれない、などと教え込まれていた庶民にとっては、とても食べられたものではなかった。肉食が一般的になるのは、明治維新を待たなければならない。
ともかく、12月14日の討ち入りに備えて、赤穂の浪士は牛肉を食べて滋養強壮に励んでいた。それが生類憐れみの令の元禄年間の出来事であって、江戸時代から肉食はあったという歴史の裏側。もっとも、それ以前に『忠臣蔵』すら人々の記憶から消えて行く時代がくるのかも知れない。