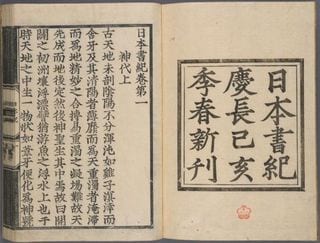(文:吉村 博光)
今年は、ノンフィクションに動きがあった年だと思う。途轍もないビッグヒットがあったわけでも、当たり年だったわけでもない。エビデンス重視の世の中で私的な感覚を言うのも憚られるが、私は潮流の変化を感じた。
年末に読んだ開高健賞受賞作『聖なるズー』は刺激的で今後さらに話題になる予感があるし、2年目をむかえた本屋大賞ノンフィクション本大賞受賞作『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』はすでに大きな話題になっている。
歴史ある賞だけでなく影響力をもつ賞が新たに生まれたのは、画期的な出来事だ。そして近年、ノンフィクションを世に出す新たな装置も生まれている。noteなどのweb上の有料閲覧システムだ。そこで生まれた本で、今年私が最も注目した本がこの『つけびの村』だ。
伝統的な手法にはない生々しさ
発生当時「平成の八つ墓村」として話題になった、2013年に起きた連続放火殺人事件を追ったルポである。出版社に持ち込んだがボツになった原稿をnoteにあげたところ人気になり、単行本化されたものである。noteがなければ、本になっていなかっただろう。
さて、ここで紹介した3作品には共通点がある。対象を俯瞰的に捉え事実を提示するのではなく、対象の中に入り自分の主観を交えて表現するスタイルなのだ。私は、伝統的な手法にはない生々しさというか、今風にいうとエモさを感じた。
『聖なるズー』は著者の経験が作品に観点を与えているし、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は母親視点が大きなポイントになっている。『つけびの村』は、著者独特の生活者視点が日常性のオドロオドロしさの味付けをしている。