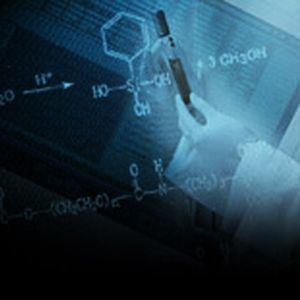震災を契機とした輪島市の“新たな地域自治”とは
鍵は“水平的ネットワーク”と“キーパーソン”の存在
2016.9.13(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください
本日の新着

張又侠粛清で「そして誰もいなくなった」状態の中国軍中枢、これから起きるのは「軍の機能不全」か「台湾有事」か
東アジア「深層取材ノート」(第316回)
近藤 大介

「夢は何ですか?」「目標は?」と聞きすぎる社会はしんどい、髭男爵・山田ルイ53世が語る生きづらさの根本
【著者に聞く】「キラキラしてないとダメ」という圧は時には暴力に、引きこもりを美談にされる違和感
飯島 渉琉 | 髭男爵・山田ルイ53世

なぜAIエージェントに調査を頼むとイマイチな報告が上がってくるのか?AIのレポート精度を上げるプロンプトの特徴
【生成AI事件簿】AIエージェントが陥る4つのパターン、行動の幻覚、制約の無視、主張の幻覚、ノイズ支配を防ぐには
小林 啓倫
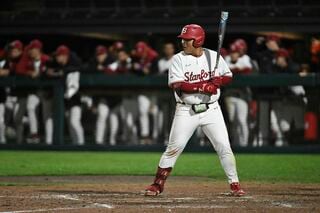
スタンフォード大の佐々木麟太郎選手が結んだ驚きのスポンサー契約、「メジャーに挑戦」が高める選手のブランド価値
田中 充