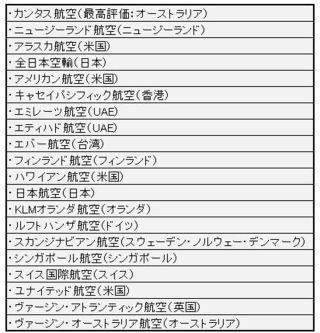日本企業の将来を左右する「ひとみ」事故の根本原因
100万台のサーバーを管理するグーグルに学ぶこと
2016.6.6(月)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください
科学技術の現場 バックナンバー

安藤忠雄設計の「直島新美術館」オープン、安藤氏9番⽬の「ヴァレーギャラリー」以来3年ぶりの新作
宮沢 洋

西池袋にある“ぼやっとした”領域、大手デベロッパーが関わらない街づくりが生きるニシイケバレイ
宮沢 洋

なぜ旧宅を壊して建て替えた?無名の建築家・岡秀世とは?静かな住宅街で静かな存在感を放つ熊谷守一美術館
宮沢 洋

【建築視点の万博】若手建築家20組を全紹介(東側エリア):注目株が輝き、冴えていた藤本プロデューサーの差配
宮沢 洋

【建築視点の万博】若手建築家20組を全紹介(海側エリア):素材と構成に注目、残念石からグネグネ樹脂壁まで
宮沢 洋

【建築視点の万博】若手建築家20組を全紹介(西側エリア):学会賞受賞者2組らが新たな屋根を競う
宮沢 洋