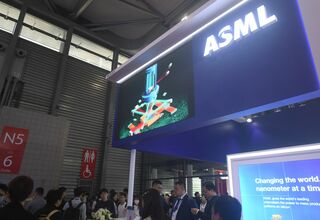水野氏は「プチジビエは、経済的な側面よりも精神的な側面が大きい」と語る。自然の恵みとして昆虫を採取・摂取することで「生態系のなかで生かされていること」を感じ、自然への認識を高める機会を提供している(冒頭の写真)。
プチジビエに参加した30代女性は「見た目に抵抗はありましたが、ほとんどの昆虫は想像よりはるかに美味しかったです。クワガタの幼虫は魚介類に近い味でしたが、カブトムシの幼虫は土臭くて食べられませんでした。クワガタは朽木を食べ、カブトムシは腐葉土を食べると聞いて、改めて自然との関わりを実感しました」と話す。
同じく参加者で、ギリシャ出身の29歳男性は「昆虫食の経験はなかったので、新しい食に対する興味で参加した」と言う。「フライにした昆虫は、パリパリの食感で、虫自体の味はほとんどわからなかったよ」と教えてくれた。
欧米では先端的で「オシャレ」な食事?
海外に目を向けると、欧米でここ数年、興味深い動きがある。“オシャレ”な家庭用・昆虫養殖器が発表されているのだ。
オーストリア出身の工業デザイナー、キャサリーナ・ウンガー氏によって制作された食用ウジムシ(アメリカミズアブの幼虫)の養殖キット「FARM432」は、1グラムの卵が432時間後には2.4キログラムの幼虫として収穫できるというものだ。
さらに、アメリカの工業デザイナーのマンスール・オラサナ氏は、キッチン用品ブランド「キッチンエイドR」とコラボレーションした食用バッタの養殖器「Lepsis」を発表。2014年にアメリカのヴィルチェック賞を受賞するなど注目を集めている。
自己管理のもとで、新鮮な昆虫を得られ、キッチンインテリアとしてもお洒落な養殖キットが普及すれば、昆虫食への抵抗感も軽減されるだろうか。こうした欧米の昆虫食ビジネスへの参入も、FAOの報告・提案を受けてさらに活発になっているようだ。食糧危機に対する意識が根底にあることに違いはなさそうだが「もともと昆虫食になじみの薄い欧米では、昆虫食をエコ、アートの対象として先端的なものと捉えているのではないか」と水野氏は話す。