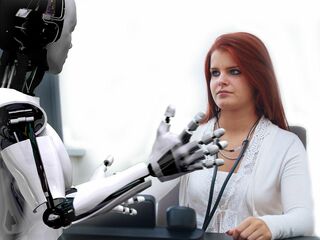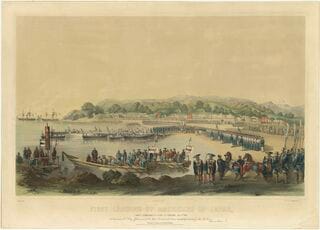日本は戦後、「軽武装・経済外交」の“吉田ドクトリン”と呼ばれたものに振り回されてきた。軍事力の脅威的な増強で覇権確立を企図する中国に対処するため、米国がアジア重視戦略に転換したにもかかわらず、日本は同盟を深化させる有効な行動が取れないジレンマを抱えている。
“吉田ドクトリン”はあったのか?
吉田茂は再軍備には正面から反対したが、独立後の国土防衛に危惧があった。そこで基地貸与で米軍の駐留に協力する方法をとった。しかし、朝鮮戦争の勃発で、GHQから警察予備隊などの整備指令を受ける。
それには外敵の侵入に対して国土防衛に任ずる性格が加味されており、日米相互安全保障条約の前文に「防衛力漸増」の文言を織り込むことで米国の要望に応えるものと考えた。
吉田は再軍備の問題が議論になると、社会党などの野党が不平等などと言う批判に対して、決然と言い放った。
「自らその愚を表白するものである。共同防衛の体制において、不平等などという観念の入り込む余地のないほど、共産攻勢は緊迫せる状態になっているのである。不平等条約論を事々しく論じたり、中立外交を唱えて得々たるものの如きは、井底の蛙鳴(あめい)、聞く度にあきれざるを得ない」(吉田茂著『回想十年』、以下同)
問題は“戦力”の解釈にあった。当時は「近代戦争を遂行する程度に達した軍事的装備をなす場合には、憲法によって保持を禁ぜられる。しかし、その程度に達しない方法によって防衛的措置を講ずることは、第9条第2項の関するところではない」としている。
また「米国から再軍備を要請されたらどうするか」との質問には、「憲法の条項は飽くまでも守るべきである、仮に再軍備の要求があっても受諾すべきではない」と答弁している。
再軍備に対しては反対論、違憲論ばかりでなく、改憲して再軍備せよ、あるいは違憲に非ずと主張するものもあった。しかし、吉田は「自衛の方途については考えねばならないが、再軍備はすべきでない」と主張し続けている。
そうした理由として「国の安全は国民自らの手で守るべきは勿論であるが、これを直ちに再軍備に結び付けて軽々に論断することは、私のとらざるところである。わが再軍備論はすでに不必要な疑惑を中外に招いており、また事実上、敗戦後のわが国力は強大なる軍備に堪え得ないことは明らかである。一国の安全独立は軍備のみの問題ではなく、頼むべきは国民の独立自由に対する情熱である」と説明する。
吉田の“再軍備”は「自衛(の程度)」を超える「強大な軍備」の謂いであることが分かる。
この説明に対する質疑応答で、「再軍備は未来永劫しないと言っているのではない。現下の状況においてこれを致すことはしない、とこう申しておるだけの話である」と補足している。
また、「講和独立の後に、その国防を米国の巨大なる戦力に託することは、最も自然且つ当然なる順序である。(中略)その後今日に至るまで論争の止まざるは、私からすれば馬鹿げたこと、不可解の感を深うせざるを得ない」とも言う。