日本では梅干を漬けるとき、シソの葉で着色してきましたし、豆腐を作るときにも「にがり」を使ってきました。また、西洋では肉を保存するとき岩塩を使ってきました。保存性が高まるだけでなく、肉の色や風味も高まることも経験的に知っていたわけです。
──その後、人工的に作るようになっていったわけですか?
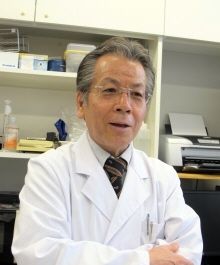 堀江正一(ほりえ・まさかず)
堀江正一(ほりえ・まさかず)大妻女子大学家政学部食物学科教授。東京理科大学大学院理学研究科修了。薬学博士取得。日本食品衛生学会常任理事。専門分野は食品中に含まれる有害化学物質の安全性評価や、食品添加物の安全性と有用性に関する研究。
堀江 ええ。例えば、岩塩がなぜそうした効果を発揮するのか調べてみたら、岩塩に含まれる硝酸という物質が、肉汁の中の微生物により亜硝酸になることが分かりました。そこで、人工的に作った亜硝酸塩を使うようになったわけです。
その技術を応用して、ハムやソーセージなどの色や味をよくする亜硝酸ナトリウムという物質も使われるようになりました。
人工的な食品添加物が使われるようになった背景には、純度の高い物質を合成できるようになったという、科学の進歩があったわけです。
──食品添加物を使う上での基本的な考え方はどのようなものでしょうか?
堀江 まず安全性、そして有効性が科学的に認められているものを使う、ということが主な基本的要件になります。
安全性については、ラットやマウスを用いた種々の動物実験で安全性を確認する必要があります。また、「国際的に安全性が評価され、米欧を含め世界で広く使われている」ということが、国が食品添加物の使用を認めるときの指針としてあります。国際的な評価とは、世界保健機関(WHO)と国際連合食糧農業機関(FAO)による合同食品添加物専門家会議(JECFA)が行うリスク評価を言います。ここで安全性が認められているかどうかということです。
有効性については、その食品添加物を使うことで、食品の品質保持や食品の製造に役立つといった効果が実証され、消費者に利益がもたらされることが当てはまります。










