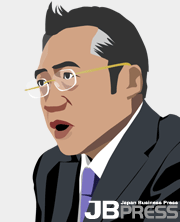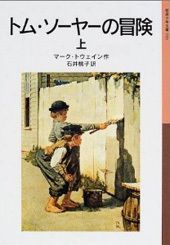市場が最も注目する大企業製造業の景況感を示す業況判断指数(DI)は、前回調査(2009年12月)の▲25から▲14と、依然としてマイナス圏ながらも絶対値は縮小し、企業経営者の景況感が改善の途上にあることが確認された。さらに市場にとってポジティブサプライズだったのは、大企業非製造業のDIが▲21から▲14へと、製造業と同じレベルに改善した点だ。
このところ、新聞に「デフレ」の文字を見かけない日はない。テレビのニュースショーはこぞって低所得者の困窮ぶりを映し出し、ニュースを見るたびにげっそりとした気分になる。しかし、その一方で、年明け以降「星」付きレストランや箱根などの高級旅館の予約が取りづらくなっている──という景気のいい話もチラホラと耳にするようになった。
さては、いまだ成長余力の大きい中国から観光客が押し寄せてきているのかと思いきや、値段の張るところほど日本人比率が高いそうだ。米国ではクルーズ船運営大手のカーニバル、宝飾品のティファニーなど高額品を扱う企業の業績回復が顕著。日本でも資産効果が表れ始めているのだろうか。
「時価総額100兆円増」は株価上昇のスタートライン
米国ではティファニーの業績好調。資産効果が表れ始めている〔AFPBB News〕
4月1日の取引終了時点で、東証1部の時価総額は331兆円となった。2009年3月12日の229兆円のボトムから見れば、100兆円余り増えた計算になる。1995年以降の株式市場で「時価総額100兆円以上増」は、2回の記録が残っている。
1度目は98年10月15日の231兆円という起点から99年4月8日の333兆円までの局面。所要期間は半年足らず。2度目は2003年の3月11日の221兆円から2004年の2月27日の323兆円まで。この時は1年近くを要した。
今回は100兆円増に1年余りとさらに時間がかかった。ただ、1998年はアジアの経済通貨危機を背景に世界的に株価が下落する中で、いわゆる「ITバブル」が萌芽し、その中心地である米国の株式市場を先導役に、世界的に急ピッチに株価が回復した時期だった。2003年の3月は日本の不良債権問題の最終盤で、日本株の下げが突出していた。世界経済はイラク問題を抱えながらも、ITバブル崩壊の荒廃から立ち直ろうとしていた時期に当たる。
2008年9月のリーマン・ブラザーズの破綻は「100年に1度の大津波」となって世界経済に襲いかかった。そのショックからの立ち直りとあれば、以前よりも「100兆円増」に時間を要しても当然。逆に、よくぞ1年余りで到達できたと言うべきだ。
そして、声を大にして言いたいことは、過去、時価総額の復元局面で「100兆円増」は通過点に過ぎなかったという事実である。1998年10月を起点とする局面の終点は2000年2月7日の452兆円で、2003年3月の上昇局面の終点は2007年2月26日の583兆円だった。今回の上昇局面がどこに行きつくのかは「神のみぞ知る」だが、4月1日の331兆円で復元終了ということは無いだろう。