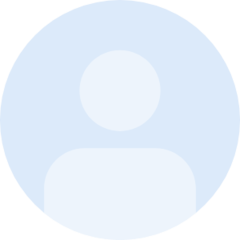写真提供:CFOTO/共同通信イメージズ
写真提供:CFOTO/共同通信イメージズ
日本をはじめ世界各国で進む超長寿化社会。これまで「老後」「シニア」とひとくくりにされてきた世代は、今や多様な価値観とライフスタイルを持つ「新しい消費者層」と再定義されつつある。本稿では『超長寿化時代の市場地図 多様化するシニアが変えるビジネスの常識』(スーザン・ウィルナー・ゴールデン著、佐々木寛子訳/ディスカヴァー・トゥエンティワン)から、内容の一部を抜粋・再編集、3200兆円規模とも言われる、長寿市場におけるビジネスの可能性を論じる。
スポーツシューズメーカーのナイキや、アイウェアのD2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)企業ワービー・パーカーは、長寿マーケットの需要をどう取り込んだか?
事例2
高齢アスリートを発見したナイキ
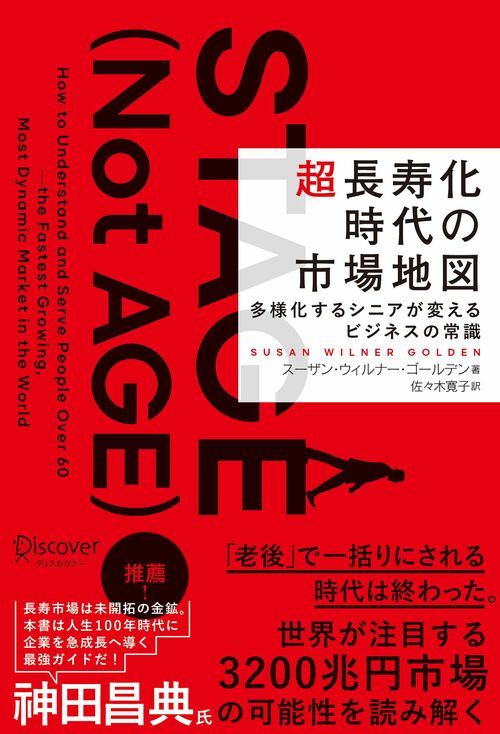 『超長寿化時代の市場地図』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
『超長寿化時代の市場地図』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
企業の戦略は、18歳から34歳の層ばかりを狙いがちだ。かつてのナイキもそうだった。スポーツシューズとアパレル販売で世界一となり、370億ドルの帝国を築いたナイキも以前は、主にこの層に向けて商売をしていた。
2019年、ナイキは、高年齢層アスリートのニーズに対応する戦略の拡大を決定した。この層は同社の売り上げの10%を占め、他の層よりも購入単価が高い。ただし、同社は高齢者向けのスニーカーではなく、「年齢を重ねるアスリート」のためのスニーカーを作ろうと決めた。
カテゴリー・プロダクト担当役員(当時)のマイク・スピレインは、ナイキの長寿カスタマー像を理解するための作業に着手した。ターゲットは現役ランナーだ。競技大会にも出続けており、今では「スローランナー」になってきた人である。
スピレインは、多くの高齢者が健康のためにウォーキングをしていることも知っていた(米国では健康のためのウォーキング人口は1億1000万以上、ジョギング人口は6000万とされている)が、それでもナイキは「ウォーキングをする高齢者」をターゲットにはしなかった。
狙いはあくまで、「ウォーキングをする高年齢のアスリート」である。スピレインは、ナイキが長年培ってきた商品へのロイヤリティを、「自分はまだまだアスリートだ」と考えている人たちから獲得する方法を見つけようとしていた。ナイキが目指したのは、「永遠のアスリート」「アスリートであり続ける人」を取り込むことだった9。
9 Robert Chess and Jeffrey Conn, “Nike: Sport Forever,” Case E690(Stanford, CA: Stanford Graduate School of Business, 2020)