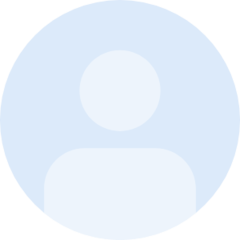写真提供:©Jimin Kim/SOPA Images via ZUMA Press Wire/共同通信イメージズ
写真提供:©Jimin Kim/SOPA Images via ZUMA Press Wire/共同通信イメージズ
日本をはじめ世界各国で進む超長寿化社会。これまで「老後」「シニア」とひとくくりにされてきた世代は、今や多様な価値観とライフスタイルを持つ「新しい消費者層」と再定義されつつある。本稿では『超長寿化時代の市場地図 多様化するシニアが変えるビジネスの常識』(スーザン・ウィルナー・ゴールデン著、佐々木寛子訳/ディスカヴァー・トゥエンティワン)から、内容の一部を抜粋・再編集、3200兆円規模とも言われる、長寿市場におけるビジネスの可能性を論じる。
米金融機関メリルリンチ(現バンク・オブ・アメリカ)は、長寿化のビジネスチャンスをどのように捉えたか?
事例1
クライアントの「100年人生」をプランニングするメリルリンチ
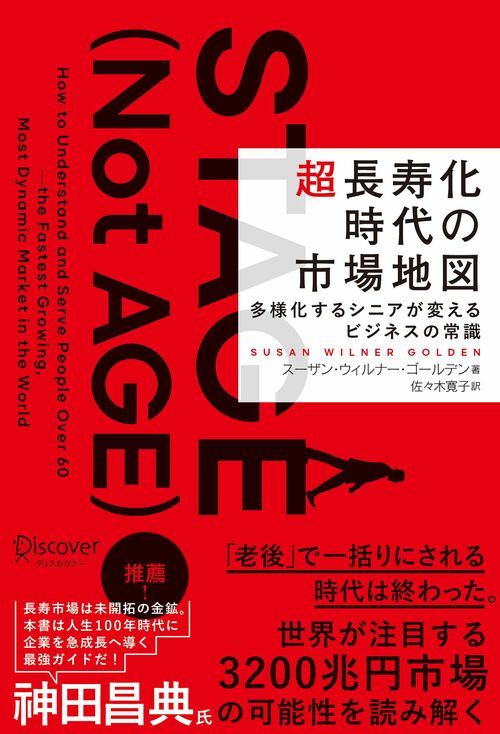 『超長寿化時代の市場地図』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
『超長寿化時代の市場地図』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
金融サービス業は、長寿化のビジネスチャンスに最初期に気づいた業界の1つだ。ユーザーが長生きするようになり、延びた寿命分の生活を支える資産が必要となったためだ。
残念なことだが、50歳以上の過半数が「老後の生活を支える資金が足りない」と回答している。こうした経済的不安は大きな国民的課題であり、今後、大きな財政課題にならないよう、国民に行動の変化を呼びかける必要がある。
業界としても、クライアントが長寿に備える意識を持つようになれば、優先順位の判断や資産運用のニーズが生まれ、事業成長の強い牽引力となるだろう。
フィデリティ証券、メリルリンチ(現バンク・オブ・アメリカ)、プルデンシャル証券などは、長寿化に伴う機会と課題を理解するために多大な投資を行ってきた。メリルリンチは業界に先駆けて事業戦略と人材戦略に長寿化を織り込み、従業員の長寿化に即した福利厚生を整備している。
メリルリンチは、クライアントの高齢化を不安視するのではなく、積極的に長寿化を事業のコア要素として戦略を策定した。この判断は理にかなっている。富の80%以上は65歳以上の管理下にあるのだから1。
1 Susan Golden and Laura. L. Carstensen, “How Merrill Lynch Is Planning for Its Customers to Live to 100,” Harvard Business Review, March 4, 2019.