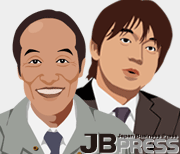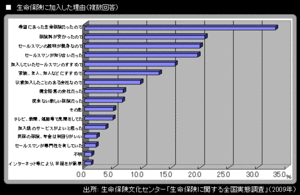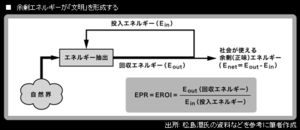米写真家ユージン・スミスがいなかったら、水俣病が国際的に注目されることはなかったかもしれない。いや日本国内でさえ、その悲惨さをどれほどの人が知っただろうか。彼は熊本県水俣市に住み着き、日本語のできる妻を通訳に、町の日常を写し続けた。
代表作の「入浴する智子と母」。母親が胎児性患者の娘を風呂の中で抱きかかえ、じっと見つめている写真である。この1枚だけでも、有機水銀中毒による公害の非人間性をあますところなく告発している。
高度成長優先の政策がもたらした悲劇
スモッグでかすむ北京の空(2008年撮影)。かつては日本でも、人の暮らしやすさよりも、産業、経済成長が最優先された〔AFPBB News〕
その水俣病について、発生は産業高度化を優先した「政策の結果」とある官僚が表現した。こういうことだ。当時は敗戦の虚脱状態からようやく抜け出し、欧米の背中を追って高度成長への坂道を駆け上がろうとしていた時代である。産業政策も軽工業から重化学工業へとギアチェンジされていた。
重化学工業にとって、プラスチックの成形などに使われるアセトアルデヒドは必需品である。その必需品を生産するのに、水俣は極めて適していた。何しろ阿蘇水系の豊富な電力があり、廃水を捨てる海が目の前にあり、塩田事業に従事していた余剰労働力がある。好条件が重なり、新日本窒素肥料(現・チッソ)水俣工場は、日本の当時のアセトアルデヒド生産量の約4割を生産していた。
一方、その頃の就業人口構造は、まだ第1次産業への就労者の比率が高かった。水俣では当然、漁業人口が多い。が、彼らには現金収入はほとんどない。そのため主たる食材は水俣湾の魚である。彼らが日常的に食べる魚は、平均的な日本人が食べる通常の量の7~8倍にも達していた、という。
しかし水俣湾にはチッソの工場から、アセトアルデヒド生産の触媒として使用した水銀混じりの廃液が垂れ流されていた。湾内で生物濃縮が起こり、最後に、その湾で育った魚を大量に食べる漁民に水銀中毒が発生するのは当然だった。