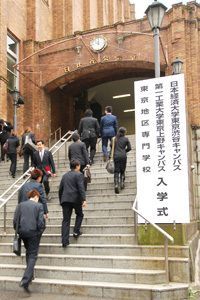従来型エビ養殖が不毛の土地を産む
富栄養化や抗生物質などの薬品投与による土地の荒廃が深刻化している(資料写真=インドネシア カリマンタン島西部のエビ養殖場)〔AFPBB News〕
残り0文字
東南アジアなど日本向けのエビ養殖場では、育成槽の底に溜まった沈澱物がヘドロ化し、3年も経つと使えなくなってしまう。このため、数年置きに、隣接地に養殖池を掘り、養殖場を移動していくのだが、いったん、ヘドロ化した池は、埋め戻しても、二度と農業に使うことができないそうだ。
エビ好きの日本人は、年間25万トン超のエビを消費する。このうち9割を輸入に頼っており、その多くが東南アジアを中心とする養殖エビだ。三上IMT社長は「供給元の国に、養殖にも農業にも適さない砂漠のような土地を生み出しながら、私たちの食生活が成り立っている。もちろん、私たち自身も、抗生物質を浴びて育ったものを口に入れるというリスクを取っている」と指摘する。
ISPSは、そうした現実へのチャレンジだ。
薬品を使わずにエビを育てるためには、他にも、様々な仕組みがある。そもそも、屋内型養殖としているのは、渡り鳥の飛来や、飛散農薬による水の汚染リスクを低減するため。養殖場内に入るには、土足から場内専用の長靴に履き替え、手はアルコールで消毒し、雑菌が水槽に入らないように配慮している。
SPF(Specific Pathogen Free=特定の病原菌を持っていない)証明書付きの稚エビを輸入し、餌も、水の中でも溶けて形が崩れないよう、植物性低タンパクを中心とする独自レシピで開発した。
回収した餌の食べ残しや糞、死エビは、乾燥させて農業肥料などとして再利用するほか、水の交換の際にも、水質基準以下に浄化した上で排水するので、環境汚染を引き起こすことなく、同じ場所で、長期にわたって事業を続けることができるという。
三重苦にあえいでいた新潟県
このような、新しい発想の養殖プラントの第1号施設が新潟県妙高市にできたのには、深い訳がある。
「雪国と都会の格差解消」「国土の均衡ある発展」を唱えて、多くの公共事業を新潟県に誘致した田中角栄元首相時代の名残で、新潟県内には建設業者、土建業者が溢れている。ただでさえ仕事の奪い合いで疲弊していたところに、小泉政権期の構造改革路線で公共事業は激減した。その上、温暖化の影響で冬期の貴重な収入源である除雪事業も減ってしまい三重苦にあえいでいた。
妙高雪国水産の母体企業である岡田土建工業も、例外に漏れず、雇用維持に四苦八苦していた。公共事業だけでは食べていけず、個人向けのコンクリート住宅の施工、食品残渣を利用した廃棄物再資源化プラントの運営、有機肥料を使用した農業経営など、事業多角化を余議なくされていた。
 岡田土建の資材置き場だった場所が、今や、エビの養殖場に
岡田土建の資材置き場だった場所が、今や、エビの養殖場に
そんな折、県内産業の構造問題に頭を悩ませていた泉田裕彦新潟県知事や、入村明妙高市長がISPSの誘致に積極的だったこともあり、陸上でのエビ養殖という未知の事業に踏み出す決断をしたという。
バナメイは、他のエビに比べて淡水への順応力が高く、水道水や地下水に独自の栄養塩を添加するだけでいい。このため、内陸にある妙高市でも養殖が可能。岡田土建の資材置き場を活用して建設した養殖場では、この春から、商業生産を本格化させている。
 妙高ゆきエビの収穫作業。漁業の経験が無くても大丈夫!
妙高ゆきエビの収穫作業。漁業の経験が無くても大丈夫!
屋内型施設のため、風雨や寒暖差などの自然環境の影響を受けることがなく、水質や温度管理はコンピューターによる自動制御。養殖場内では、餌まきや、収獲など軽度の単純作業が中心なので、土木会社出身の未経験者ばかりでも、運営は順調だ。
妙高雪国水産の宮越隆事業所長も、岡田土建からの転身組。「東南アジアの養殖エビに比べれば価格競争力では圧倒的に不利。それでも、薬品を一切使わずに育て上げた安全・安心の価値を分かってくれる人はきっといる」と販路開拓に奔走している。
 収穫後、新鮮なうちに真空パックに。コメに次ぐ、新潟の名産品になれるか?
収穫後、新鮮なうちに真空パックに。コメに次ぐ、新潟の名産品になれるか?
三上IMT社長も、「世界的な気候変動、新興国の人口増加による食糧不足を考えれば、環境に負荷を与えず、安全な食物を生産する養殖は、これからの成長産業。日本中にISPSの技術を普及させたい」と意気込む。1号プラントで生産する妙高ゆきエビが市場に受け入れられるか、今、まさに正念場だ。
次回(16日)は、プラントを開発したアイ・エム・ティーの野原節雄専務ら、キーマン3人にスポットを当てて紹介する。