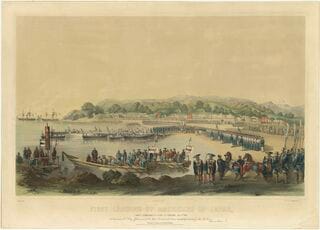かつての黄金都市と廃墟
アユタヤ朝は、王都を造るにあたりスコータイ朝を受け継ぎ、上座仏教を国の支えとした。上座仏教とは、中国から日本に伝わった全ての衆生の救済を目指す大乗仏教と異なり、それぞれの個人の悟り“涅槃”を重んじるスリランカから伝来した教えである。シャム王自らが敬虔な仏教徒になり、誰にもなしえない至高の布施を行うのだ。
そのため歴代33人の王により、インドのストゥーパに由来する仏塔(チェディ)が無数に建てられ、都中に立ち並んだ。王宮内にあったワット(寺)・プラシーサンペットには、天を突く高さ35mの釣り鐘型のチェディが3基そびえる。仏塔とは、本来は釈迦の遺骨(仏舎利)を納めるためのストゥーパが原型だが、ここでは3人の王の遺骨が埋葬された。積み上げられた赤レンガとそれを包みこむ白漆喰が、タイの青空に映えて、凛とした美しさを際立たせている。
アユタヤの独自性は、こうした仏塔や寺院がすべて赤レンガで組み立てられ、石積みでも木造でもないこと。レンガ造りの上に白漆喰をぬり込み、精緻なデザインや神々の像を飾りたてた。その表面が、かつては黄金色に輝いていたと伝わる。
黄金伝説を裏付けるようにワット・ラーチャブーラナの、トウモロコシ型になった堂塔の地下空間には、15世紀の金製品が総数1万点も納められていた。それらはルビーやサファイアなどの宝石をはめ込んだ、王権を象徴する神器のミニチュアである。なかでも目を瞠るのが、背に王が乗る輿をくくりつけた“金象”の躍動感だ。アユタヤの宮廷文化の中で、金属工芸もまた研ぎ澄まされていった。
現在は史跡公園として整備されているアユタヤだが、滅亡から250年という時の流れを背負った廃墟がある。それがワット・マハタートで、漆喰がはがれ落ち、壁のレンガ積みは歪んで波打っている。台座の上に14~15体ずらっと石仏(上座仏教ではブッタ像)が居並ぶが、それら坐像の顔という顔はみな落ちていた。
息をのむのは、1個の仏頭が大きな木の根に絡みとられ、目を伏せうっすら笑みを浮かべながら宙に浮いているのだ。ビルマ軍が容赦なく仏像の首を落とし、その内のひとつが菩提樹の根に包みこまれ、偶然いま“奇跡の姿”を留めているに違いない。菩提樹とは、釈迦がその下で悟りを開いた木である。
不動産のオリジナル性を尊重する世界遺産からはかけ離れるが、そんな仏頭や首なしブッダ像、波打つレンガ壁こそがアユタヤを象徴する文化財ではなかろうか? 修復したらそれは消えてしまう。
タイの中で一番綺麗だと聞く“アユタヤの葬式”は、王都ならではの華やかさに満ちていた。夜空にきらめく電球の灯りの下、宮廷を想わせる楽団がリズムを奏で、金襴の衣装をまとった踊り子が舞う。その上座に92歳で大往生したプーン爺さんは、納棺され横たわっている。亡骸(なきがら)は寺に100日間安置してから、その庭で祭礼を楽しませながら荼毘に付すのだ。
庭の側では即興歌劇リケーが演じられ、村人たちが茣蓙の上で楽しんでいる。仕掛けたナイアガラ花火に、プーンさんの名前が浮かび上がった。やがて盆踊りの櫓みたいな火葬台で、お爺さんはゆっくりと灰になってゆく。タイには墓がない。火葬された遺灰の多くは、川や海に散骨され自然に還されるのだ。
こうした伝統や風習、工芸などの手技は、不動産を構成資産にする世界遺産には含まれない。けれども「アユタヤ歴史地区」の醍醐味は、人々が受け継いできた暮らしに宿っている。屋台のクレープ生地で巻いた綿あめ・名物ロティサイマイさえ、だから愛おしい。
(編集協力:春燈社 小西眞由美)