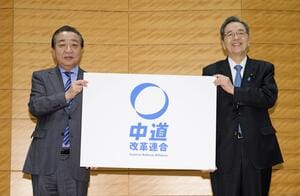氷河期世代の集団就職説明会(1995年、写真:Fujifotos//アフロ)
氷河期世代の集団就職説明会(1995年、写真:Fujifotos//アフロ)
(川上 敬太郎:ワークスタイル研究家)
四年生大学卒の就職者割合が55.1%にまで低下した「氷河期世代」
参議院選挙戦で掲げられた各政党の公約を確認すると、就職氷河期世代の支援を訴えるものが多く見受けられます。1994年に新語・流行語大賞に選ばれ、直近でも年金制度改革による影響が指摘されるなど、就職氷河期世代は折に触れて注目を集めてきた層です。
就職氷河期世代とは、1993年から2004年にかけて新卒で就職活動を行った人たちを指します。いわゆるバブル経済が崩壊し、各社が新卒採用枠を大幅に抑制したことで就職に非常に苦労した世代でした。
数にしておよそ1700万人とも言われる就職氷河期世代は、有権者のおよそ16%を占めるボリュームゾーンです。各政党が注目するのは当然かもしれません。私自身もこの世代に該当しており、同じ年に生まれた人数が200万を超えた団塊ジュニア世代でもあるので、受験や就職など、子どもの頃からあらゆる局面で激しい競争にさらされてきました。
実際、就職氷河期世代が苦しい思いをしてきたことは確かだと思います。その苦しさに焦点が当てられるようになったことには、大いに意義を感じます。ただ、果たして本当に、就職氷河期という世代だけを特別視して行われる支援は有意義なのでしょうか。
文部科学省の「学校基本調査」によると、四年制大学卒業者に占める就職者の割合は1991年には81.3%を記録していました。ところが、就職氷河期の始まりとされる1993年には76.2%へと落ち込みます。
そこから多少の上下はありながら下降していき、2003年には55.1%にまで低下しました。1991年との落差は、26.2ポイントにも及びます。そんな就職氷河期世代に注目が集まったことによって、生まれた年が違うだけで困難な状況へと追い込まれてしまう理不尽さを多くの人が認識しました。
その困難の影響は、厄介なことに一生ついて回ります。新卒採用枠に入れなかった人は、不本意ながらアルバイトやパートなど非正規社員と呼ばれる雇用形態を選択するか、無職の状態に置かれることとなりました。
やがて正社員として中途採用されたとしても、社歴の差が給与や昇進に響き、新卒入社組との格差は埋まらないまま続いていきます。
さらには、厚生年金の加入期間や収めた保険料に差が生じて受け取り年金額が少なくなってしまうなど、社会の入り口でのたった一度のつまずきが人生を通してのハンデとなり、マイナスの影響を及ぼすことになってしまうのです。これこそが、就職氷河期問題の根幹に他なりません。
原因となっているのは、いわゆる日本型雇用システムが有するさまざまな構造上の瑕疵(かし)です。中でも3点挙げたいと思います。