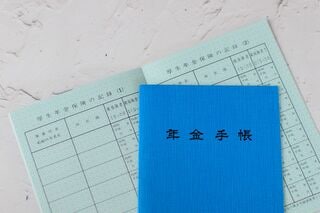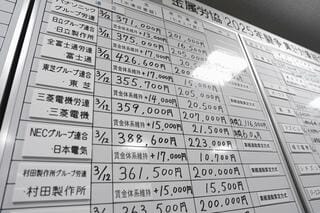今後10年で親の介護を迎える就職氷河期世代(写真:GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート)
今後10年で親の介護を迎える就職氷河期世代(写真:GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート)
就職氷河期世代の介護者が200万人に増える──。自身も10年以上の介護経験がある介護福祉ジャーナリストの奥村シンゴ氏は、7月の参院選でも争点になりそうな氷河期世代対策において、「向こう10年で(氷河期世代の)介護者が急増する」という問題がほとんど語られていないと指摘する。どういうことか。
(湯浅大輝:フリージャーナリスト)
「カネ」も「頼れる人」も不足する氷河期世代
──日本総研のレポート*によると、今後10年間で、就職氷河期世代で親の介護をする人が足元の約75万人から約200万人(人口比で4.4%→11.8%)にまで拡大するとされています。奥村さんはご自身の介護経験から、働きながら介護をする「ワーキングケアラー」の限界について熟知されていますが、将来的に大きく取り沙汰されそうなこの問題、世間に広く伝わっているのでしょうか。
*50歳代を迎える就職氷河期世代の実像③― 約200万人が介護に直面する可能性、働きながら介護できる制度の整備と利用の促進を ―(日本総研・2024年2月)
奥村シンゴ氏(以下、敬称略):伝わっていないと思います。就職氷河期世代は、1700万人ほどいると言われていますが、その内の200万人、つまり約12%が介護を軸とした生活に移らざるを得ないという指摘があるのですから、これを重く受け止めるべきです。
氷河期世代特有の問題点として挙げられるのは、「お金がないこと」。現在40〜50代前半のこの世代は他の世代と比較した時、新卒採用率が低く、正社員になれた人の割合も少ない傾向にあります。
さらに、氷河期世代が生まれた時から、核家族化が急速に進行したことも忘れてはいけません。現在、介護の主な担い手になっている60代以上は、まだ大家族の名残もあり、兄弟も多かったのですが、氷河期世代以降は一人っ子も多く、家族の関係性も希薄化しています。「私しか親の面倒を見る人間がいない」という状況に置かれやすいのです。
 奥村 シンゴ(おくむら・しんご) 介護福祉ライター/支援団体「よしてよせての会」代表 宝塚出身、大阪市在住。相談支援事業所事業部長、国際ソロプチミスト神戸東クローバー賞受賞。認知症の祖母と精神疾患の母を1人で32歳から計10年面倒を見たケアラーの当事者、評論家、ケアラー支援団体「よしてよせての会」代表。読売新聞、毎日新聞、フジテレビ、共同通信、ヤフーニュース、介護専門誌他メディア多数掲載・出演。著書 『おばあちゃんは、ぼくが介護します。』(株式会社法研)
奥村 シンゴ(おくむら・しんご) 介護福祉ライター/支援団体「よしてよせての会」代表 宝塚出身、大阪市在住。相談支援事業所事業部長、国際ソロプチミスト神戸東クローバー賞受賞。認知症の祖母と精神疾患の母を1人で32歳から計10年面倒を見たケアラーの当事者、評論家、ケアラー支援団体「よしてよせての会」代表。読売新聞、毎日新聞、フジテレビ、共同通信、ヤフーニュース、介護専門誌他メディア多数掲載・出演。著書 『おばあちゃんは、ぼくが介護します。』(株式会社法研)
氷河期世代はこうした厳しい現実に直面しているのに、行政はこの世代への支援を十分に行なっていません。例えば、30代以下の「ヤングケアラー」に対してはこども家庭庁が手厚い支援策を用意していますが、40〜50代への支援に関しては十分とは言えません。
さらに、「介護離職者」への支援が途切れていることも問題です。働きながら親の介護をする人たちに対しては国・自治体ともサポートしていますが、一旦仕事を辞めてしまうと、ほとんどの支援が受けられなくなります。
まして、氷河期世代は正社員になれた人が少なく、介護休暇などに理解がある大企業勤めも少ない。中小企業で働いていて、親の介護が必要になったが、自分以外に面倒を見る人がいない。仕事を辞め、親子とも共倒れになる、という人が急増すると予想されます。
──介護施設を利用するという選択肢は取れないものなのでしょうか。