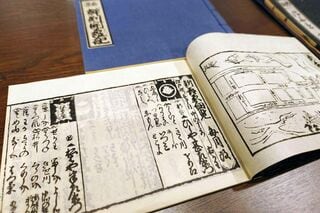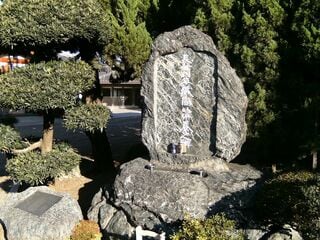大河ドラマ『べらぼう』ドイツ人医師も驚く“忘八”と呼ばれた吉原楼主への理不尽な職業差別
真山 知幸
偉人研究家
2025.6.28(土)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
大河ドラマ『べらぼう』田沼意次の失脚を招いた天明の大災害「浅間山大噴火」、その甚大な影響とは?

ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
大河ドラマ『べらぼう』田沼意次の失脚を招いた天明の大災害「浅間山大噴火」、その甚大な影響とは?