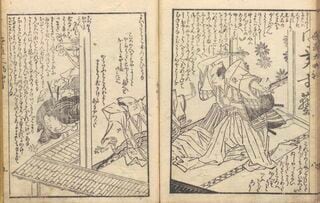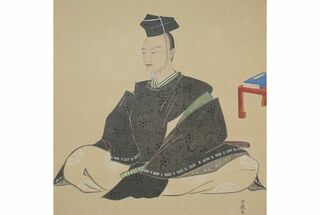佐野政言の墓がある徳本寺(東京都台東区、写真AC)
佐野政言の墓がある徳本寺(東京都台東区、写真AC)
NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第23回「我こそは江戸一利者なり」では、狂歌の指南書も見事にヒットとなり、蔦重が経営する「耕書堂」は注目の版元となった。周囲からは日本橋への出店を勧める声も寄せられるが……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)
「詠み捨て」の原則を変えた狂歌集のブーム
今回の放送では、オープニング曲明けから、桐谷健太演じる大田南畝(おおた なんぽ)のもとに人が殺到。南畝は「四方赤良(よもの あから)」という狂歌名だったことから、こんな狂歌とともに紹介された。
「高き名の ひびきは四方に わき出て 赤ら赤らと 子供まで知る」
これは、当時名をはせていた俳諧師の雪中庵蓼太(せっちゅうあん りょうた)が『蓼太句集』の序文の執筆を南畝に依頼した時に詠んだ一首とされている。「四方赤良」の名が子どもまで知れわたっているというのだから、すごい人気だ。
狂歌ブームの火つけ役となったのが、四方赤良と朱楽菅江(あけら かんこう)が編集し、748首を収めた『万載狂歌集』だ。合わせて、唐衣橘洲(からごろも きっしゅう)による『狂歌若葉集』と2冊の狂歌集が出されたことで、狂歌を取り巻く状況が一変する。
というのも、それまで狂歌は詠み捨てが原則とされ、後には残らなかった。そんななか、2冊の狂歌集が発刊され、とりわけ編集にも工夫が施された『万載狂歌集』は大きな話題を呼ぶ。狂歌師にとって「自分の狂歌が本に掲載される」という新たな目標が生まれた。
もともと売れっ子だった大田南畝は、「四方赤良」の名でも売れることとなった。ドラマでは、四方赤良のこんな歌も披露された。
「われを見て 又うたをよみ ちらすかと 梅の思はん こともはづかし」
「俺を見てまた歌を詠もうとしているな」という梅の花の気持ちを代弁。隙あらば狂歌を詠む、というくらい大ブームだったようだ。