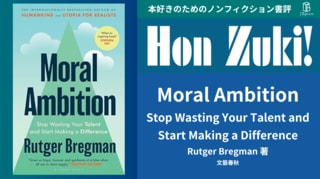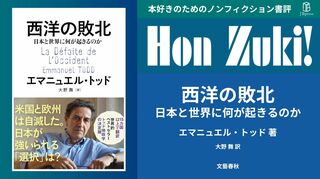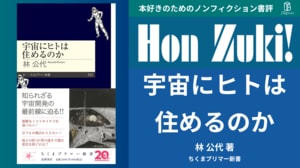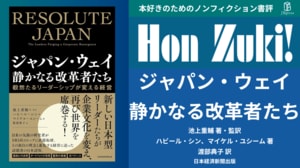進化のワープが膨大な種を生み出した
理論進化学者である著者アンドレアス・ワグナーの真骨頂、その説明は明解だ。実際の数理解析は難しそうだが、それは省かれていて、エッセンスだけが書かれている。かいつまんでいうと、進化好きにはおなじみの「遺伝的浮動」と呼ばれる上方向以外-下方向も含めて-の動きと、ある山の頂上から別の山の頂上へのワープ、が生じてきたことが説かれていく。
前者はともかく、後者などありえないと思われるかもしれないが、前著『進化の謎を数学で説く』(文藝春秋)で詳しく説明されているように、個体レベルではなく分子レベルでは頻繁に起こりうる現象である。
約40億年前に存在したと考えられる生命の共通祖先LUCAから出発し、膨大な数の種を産み出すという大成功を遂げたのが生命進化だ。その原動力はランダムに生じた変異の自然選択=上方向への移動であったが、それだけでは不十分で、時には遺伝的浮動という「ゆらぎ」が生じた。また、時には離れた場所への瞬間移動もおこなわれてきた。真っ直ぐ上に進むだけではダメで、ゆらぎと別の位置への移動が大事なのだ。本の後半は、そういったことを創造、神による創造ではなくてイノベーション的な創造、に活かす意義とその有用性が説かれていく。
「しばしば進めなくなって引き返す」ことにより「新しい道を見つけることができ、少しばかり前に進むことができた」。これは、19世紀の偉大なる科学者ヘルムホルツの言葉である。ヘルムホルツは熱力学第一法則の確立と視覚の三色説、すなわち、物理学と生理学でとてつもない業績をあげている。さすが天才、ゆらぎとワープの能力を自ずと身につけていたのだろう。
自律性、多様性、失敗の許容、知識の組み替えが進歩を促す
ゆらぎのために重要なのは「心の組み替え」である。それにより、「心の地形図を飛び越えたり、迷走できるような心の状態に到達する」ことができる。そのためには、短いスパンとしては抱えている問題から心を一旦遠ざけること、長いスパンでは旅に出ること-物理的な旅でもいいし、専門領域を渡り歩くような内的な旅でもいい-が必要だ。ゴールを直接目指すより、ちょっとした遠回りをすることが大事、「競争は不可欠だ。しかし、それだけでは十分ではない」のである。
適応度地形の思考から得ることができる子どもの教育に関する普遍的なメッセージは「多様性と自立性を育むこと」。そして、あそびも必要。言い古されたことかもしれないが、進化論からもその結論が導き出される。これは学術研究にも同じようにあてはまり、「自律性、多様性、失敗の許容、知識の組み替え」によってその進歩が促進される。残念ながら、今日の基礎研究はこれら重要なポイントを阻害するような方向にある。大きな原因はふたつ、研究の専門化と競争の激化だ。