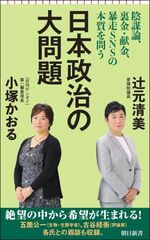暴走するSNS政治を先導するのはこの10年でスマホを手にしたシニア層、デマや陰謀論の拡散は食い止められないのか
小塚 かおる
「日刊ゲンダイ」第一編集局長
2025.6.1(日)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
告示前に景色が大きく変わった東京都議選、国政選挙の先行指標になる「SNS選挙」と「小泉劇場」の趨勢

あわせてお読みください

石丸伸二の手法にも学んだ、国民民主のネット戦略全貌 参院選へ独自の新戦略「AIファクトチェック」とは?
【西田亮介の週刊時評@ライブ】国民民主党の伊藤孝恵氏に聞く③
西田 亮介 | 伊藤 孝恵

【独自】国民民主、参院選でAIファクトチェック導入へ 誤ったSNS投稿に2時間以内に反論、偽情報の流布防ぐ狙い
JBpress

斎藤元彦に立花孝志…法と倫理の境界線を越える政治家たちは都議選、参院選と続く暑い夏を無事迎えられるのか?
兵庫県知事選をきっかけに明るみ出た構造的問題、法的制裁や社会的批判が機能不全に陥る無法状態の日本政治
山本 一郎

政治系コンテンツ「収益化オフ」は誰の口を塞ぐのか?ネット規制が新興勢力を狙い撃つ構造的リスク
【西田亮介の週刊時評】ネット規制強化が招きかねない政治・選挙への参入障壁
西田 亮介

立花孝志はいかにして民主主義をハッキングしているのか、選挙制度を揺るがすレイジベイティングの恐怖
比例当選後の辞職で議席の実質的な“売買”が可能になってしまう現実、性善説に基づく選挙制度は限界か
山本 一郎
本日の新着

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力
身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点
市ノ瀬 雅人

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に
広尾 晃

「中国が『EUV露光装置』試作機完成」の衝撃…世界の半導体秩序は抜本的に書き換えられてしまうのか?
莫大なカネとヒトをつぎ込んだファーウェイ、中国半導体版「マンハッタン計画」の行方
湯之上 隆

歯の治療費250万、孫へ贈与が500万…退職金が「蒸発」し、年金が「枯渇」する恐怖
「そこそこの貯蓄」があっても安心できない、年金生活者を襲う想定外の出費
森田 聡子
政治を読む バックナンバー

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力
市ノ瀬 雅人

維新「国保逃れ」の重すぎる罪、政治家の倫理観欠如が脅かす制度の持続性、全容解明はまだ遠い
西田 亮介

自民連立で消えゆく維新の“情熱野郎”、橋下世代の「改革魂」はどこへ?揺らぐ「既得権打破」のアイデンティティ
大井 赤亥

高市内閣・サナエノミクス実現を遠のかせる植田日銀、時期尚早の引き締めが低迷経済からのテイクオフをまたも阻む
渡辺 喜美

公明党が握る2026年高市政権の命運、維新・国民の与党傾斜で手にした政局の主導権、高支持率でも実は脆い自民の足元
尾中 香尚里

高市自民と維新が仕掛ける“対公明リベンジ”、議員定数削減で狙う大打撃、「第三極」の旗降ろす維新は消滅の道へ?
渡辺 喜美