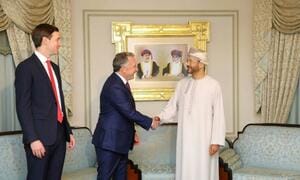ロシア国内では火災の発生件数が増えている(写真は2024年6月24日モスクワ郊外の科学研究所で発生した火災、写真:Russian Look/アフロ)
ロシア国内では火災の発生件数が増えている(写真は2024年6月24日モスクワ郊外の科学研究所で発生した火災、写真:Russian Look/アフロ)
2025年5月16日、およそ3年ぶりに開催されたロシアとウクライナの直接協議は、2時間足らずで終了した。
協議後、両国の代表団は記者団に、双方が1000人の捕虜を近く交換することで合意し、協議を続ける方向で一致したと述べたが、ウクライナが求める30日間の無条件停戦については物別れに終わった。
2025年5月19日、自分がロシアのウラジーミル・プーチン大統領と話さない限り「何も起こらない」と豪語していた米国のドナルド・トランプ大統領とロシアのプーチン大統領の米露首脳による2時間に及ぶ電話会談が行われた。
しかし、プーチン大統領は「危機の根本原因の除去」が不可欠だとする従来の立場を強調し、即時停戦に応じなかった。
これを受けてトランプ大統領は記者団に対し「何も進展がなければ、ただ身を引くだけだ。これは私の戦争ではない」と強調し、仲介をやめる可能性を示唆した。
ウクライナ停戦・和平にとって重大なイベントであったロシアとウクライナの直接協議と首脳電話会談において、双方に譲歩の意思がないことが改めて明確になった形だ。
停戦や和平の先行きはなお見通せない状況である。
ウクライナ戦争は既に3年3か月が経過した。ウクライナは、西側諸国からの支援を受けながら、徹底抗戦を続けており、戦況は停滞状態にある。
ちなみに、米紙ワシントン・ポストによると、前述したロシアとウクライナの直接協議において、ロシア代表団を率いたウラジーミル・メジンスキー大統領補佐官はウクライナ側に対し、同国の東・南部4州全域からの軍撤退を要求し、「ロシアは永遠に戦争を続ける用意がある」「この場にいる誰かが、さらに多くの愛する人を失うかもしれない」などと戦争継続を辞さない構えを強調したという。
また、ロイター通信によると、メジンスキー氏は協議で、17~18世紀に初代ロシア皇帝ピョートル1世がスウェーデンと20年以上続けた大北方戦争を例に出して「そちらが望むだけ、戦争を続ける準備はできている」と威圧したとされる。
プーチン大統領は、「ウクライナが戦場でロシアに勝つのは不可能」であると主張する。
筆者も、ウクライナは、戦場でロシアに負けはしないが勝つことはできないと見ている。
では、ウクライナはどうすればよいのか。
軍事思想家カール・フォン・クラウゼヴィッツは、その著書『戦争論』で、「現実の戦争において講和の動機となりうるものが2つある。第1は勝算の少ないこと、第2は勝利のために払うべき犠牲の大きすぎることである」と述べている。
ウクライナにとっては、西側諸国の兵器などの軍事支援の継続がなければ勝算は小さくなる。
現在、米国がウクライナへの支援を停止する懸念が強まる一方で、欧州の国々は団結してウクライナへの支援を強化しようとしている。
前回の記事「トランプ危機で瓢箪から駒、ウクライナ軍の戦闘能力を格段に上げた『デンマーク・モデル』とは」(2025.5.17)で述べたが、欧州の国々からの力強い支援があれば、ウクライナ軍は戦場で持ちこたえることができると筆者は見ている。
問題は犠牲の大きさである。
ロシア軍には兵士の死をなんとも思わない人命軽視の風潮がある。したがって、ロシアは長期戦で犠牲者が増えてもなんら問題にならない。
一方、ウクライナは、長期戦になり犠牲者が増えたら耐えられないであろう。
2022年5月21日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、地元テレビのインタビューで次のような発言をしている。
「ロシア軍を2月の侵攻開始前のラインまで押し戻せばウクライナ側の勝利である」
「ロシア側に占領されたすべての土地を取り戻すのは簡単ではないし、重要なのは、命を惜しまず戦うウクライナ軍人の犠牲を減らすことである。今、貪欲になるべきではない」
ウクライナは徹底抗戦による長期化は避けたいところである。
では、ウクライナはどうしたらいいのか。次の2つのシナリオが考えられる。
●1つ目は外交交渉による和平合意
ウクライナは負けを認めて、クリミア半島およびウクライナ東部・南部4州(ドネツク州、ルガンスク州、ザポリージャ州、ヘルソン州)のロシアへの割譲を覚悟して、停戦交渉・和平交渉に臨むことになる。
●2つ目はプーチン政権の退陣
後方攪乱工作という謀略によりロシア国民の厭戦気分を高め、大規模な反戦デモを喚起し、最終的にプーチン政権の退陣を惹き起こそうというものである。
併せて、国際社会は一致団結して、経済金融制裁でロシアを経済的、外交的に孤立させ、国際世論でプーチン氏の戦争犯罪や民族大量虐殺罪を批判し、ロシア国民の反プーチン感情を扇動する。
さて、「後方攪乱」は読んで字のごとく敵前線に対しての後方地域に工作を行いロシアの社会に混乱と動揺を惹き起こすことである。
その事例として、本稿では「明石謀略」を紹介する。
また、ロシアでは、ウクライナの後方攪乱工作とロシア人のレジスタンス運動に起因すると見られる火災が多数発生している。
これに関しては、ウクライナの公開情報の調査・分析コミュニティの「モリファル」(Molfar)の調査報告書が公表されている。
以下、初めに明石謀略について述べ、次に「モリファル」の調査報告書について述べる。