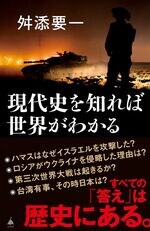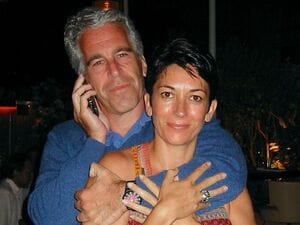トランプがどれだけ関税率をいじっても、それだけでは米国の製造業は復活しない
【舛添直言】トランプは保護主義が第二次世界大戦を招いた歴史を知らないのか
舛添 要一
国際政治学者
2025.4.12(土)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
ハーバードを恫喝するトランプの「リベラル狩り」に大衆はなぜ喝采送るのか…背景に米国の低学歴層が抱く反知性主義