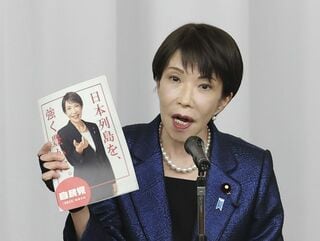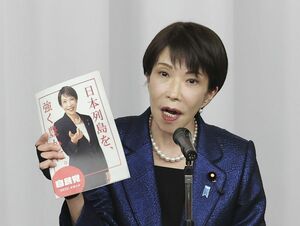東日本大震災で壊滅的な被害を受けた沿岸部(写真:共同通信社)
東日本大震災で壊滅的な被害を受けた沿岸部(写真:共同通信社)
2011年3月11日に三陸沖を震源とする大きな揺れが東日本を襲った。それを発端に、東日本沿岸には津波が押し寄せ、また、福島第一原子力発電所では深刻な原子力事故が発生した。東日本大震災である。多くの人が、大切な人、大切なものを失い、自然が持つあまりにも大きな力に畏怖した。
岩手県出身の作家・柚月裕子氏もまた、東日本大震災で心に傷を負った。震災をテーマにした小説を書こうにも、執筆をした日の夜に必ず辛い夢を見るほどだったという。それを乗り越え、柚月氏は震災直後の東北地方をモデルにした小説『逃亡者は北へ向かう』を上梓した。今回の作品を書くに至った経緯や、読むにも苦しさを伴うストーリー展開について、柚月氏に話を聞いた。(聞き手:関瑶子、ライター兼ビデオクリエイター)
※以下、本の内容を含みますので、まだお読みになっていない方はお気をつけください。
──プロローグでは、雪がちらつく中、SATのスナイパーが「真柴」という青年を狙っている様子が描かれており、物悲しく、冷たい印象を受けました。なぜあのようなかたちで物語をスタートさせたのですか。
柚月裕子氏(以下、柚月):先が分からない、不穏な雰囲気を出そうと思い、陰鬱としたプロローグを書きました。
主人公の一人である真柴亮が、どのような運命を辿るのか、読者の方はプロローグから予想して読み進めていきます。その過程で、自分が考えるのとは違う顛末を迎えるのではないか、とも思えるようにしたかった。
今回の小説は、はっきりとは書いていませんが、東日本大震災をモチーフにしたものです。震災下と同様、何がどうなるのかわからない状況の中で物語が進んでいくよう感じてもらいたいと思いました。
また、私の中で、あの震災の記憶はとにかく「冷たい」。先ほど、冒頭シーンの印象を「冷たい」と仰っていましたが、まさにその通りです。自分が五感で記憶しているものを読者の方と共有したいと考えたことも、あのシーンを描くモチベーションになりました。
──震災時の具体的な「冷たい」エピソードはありますか。
柚月:遺体安置所の「冷たさ」です。
今回の物語にも遺体安置所が何度か登場しますが、私自身、東日本大震災直後、身内の遺体を探して遺体安置所をいくつも回りました。
あの時期は、まだ寒い季節でした。その上、遺体安置所には遺体の腐敗を遅らせるためにドライアイスの塊がたくさん置かれていました。とにかく、冷たい。季節も、状況も、すべてが冷たかったのが、長い間、頭から離れませんでした。
 遺体安置所となった小学校の体育館(写真:共同通信社)
遺体安置所となった小学校の体育館(写真:共同通信社)
──今回の書籍は、2023年から週刊新潮で連載していたものを単行本化したものです。なぜ東日本大震災発生から12年という年月を経て、被災地をモデルにした小説を書くに至ったのですか。