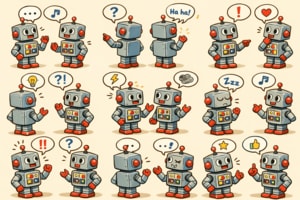そのコンテンツを生み出したのは人間かAIか?その検知システムがもたらす新たな人種差別
【生成AI事件簿】白人・英語話者のコンテンツで学習したAIはそれだけバイアスがかかっている
小林 啓倫
経営コンサルタント
2024.9.30(月)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
米大統領選を支える小口献金、生成AIが解き明かした寄付金が増える投稿、マイナスな投稿