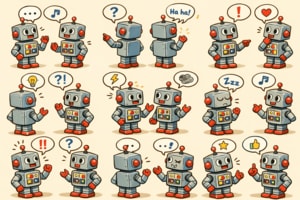デジタルウォーターマーク方式が持つ明らかな問題
デジタルウォーターマークとは、AI生成コンテンツに特別な「しるし」を埋め込む技術、あるいは埋め込まれた「しるし」自体を指す言葉だ。ただし、このしるしは、まさに
残り3495文字
デジタルウォーターマークとは、AI生成コンテンツに特別な「しるし」を埋め込む技術、あるいは埋め込まれた「しるし」自体を指す言葉だ。ただし、このしるしは、まさに
残り3495文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら