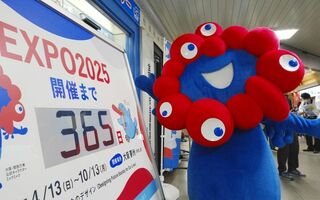2020年7月の豪雨で氾濫した球磨川。人吉市上空より(写真:共同通信社)
2020年7月の豪雨で氾濫した球磨川。人吉市上空より(写真:共同通信社)
2024年5月13日に行われた国会質問で、球磨川(熊本県)で起きた洪水の現実を、机上の計算にすり替えて、川辺川ダム計画に固執する国土交通省(国交省)の姿が露わになった。
国交相と役人の詭弁
衆議院決算行政監視委員会第4分科会で山崎誠議員は「令和2年7月豪雨を受けて新たな球磨川河川整備計画が策定され、流水型の川辺川ダムを柱とする治水対策が進められようとしている。しかし、豪雨の検証がずさんで必要な対策が実施されないとの疑念を住民は持っている」との追及を行った。住民が行った豪雨検証と国のそれとは齟齬があり、国の計画は、川辺川ダムありきではないか」という問いだ。
これに対し、斉藤鉄夫国土交通大臣は官僚の答弁原稿を読み上げて、国交省による検証の正当性を次のように主張した。
「令和2年7月球磨川豪雨検証委員会で、氾濫現象の解析、流量推定などを行った。水位計やカメラ映像、沿線住民の証言、氾濫水の痕跡など国や自治体が保有するものに加え、地図上に時系列で浸水状況を整理し、洪水で亡くなられた方の状況なども把握。本流、支流一体となった河川の水位計算や数値解析を用いて現象の再現性を確認。その結果を、河川整備計画の策定に当たって球磨川水系学識者懇談会で専門的観点から確認をいただいた」などというものだ。
山崎議員は、「大臣も認めたように齟齬がある。しかし、現場の事実はここ(書籍『流域治水がひらく川と人との関係』嘉田由紀子:編著 )に詰まっている。齟齬があるから、(国の)机上の分析とどっちが正しいか検証してもらいたい」と住民による検証との齟齬の根拠を挙げていった。
たとえば、本流の水位が上がる前に支流からの氾濫で人々が命を落としたという住民検証と、国の検証とには違いがある。
「清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」は、「3年前の豪雨球磨川水害の教訓、現行のハザードマップだけでは命を守れない」(JBpress 2023.11.1)でも既報したように、住民200人以上に対し「何時ごろ」「どちらの方向から水が来たのか」と聴き取りを行い、2000枚以上の写真や動画を入手した結果、バックウォーター現象以前に支流が氾濫し、人々が命を落としたという検証結果を出した。
一方、国の検証では、大臣を補佐する廣瀬昌由水管理・国土保全局長が答弁した通り、住民の命が失われた原因は「本流の水位が高いことで支流が合流点で合流しにくくなるバックウォーター現象」が支配的だというものだ。