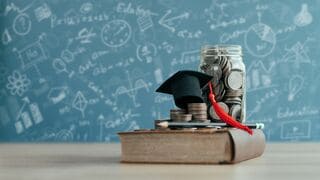現場の悲鳴「児童一人ひとりに向き合えない」
▼専科教員が配置できず、予備実験や授業準備等に十分な時間をかけることができず、満足いく授業を実施できなかった。教員の負担感、疲労感が大幅に増し、体力も低下してコロナウイルスやインフルエンザに感染した(4人)。学校が回らなくなり、休校の事態となった(熊本県小学校)
▼年度の始まりに担任がいなかったことや、途中で担任変更があったことで、こどもが戸惑い、学級が崩れてしまった。一年の始まりは、子どもにとっても担任にとっても重要なので、教員数の確保は喫緊の課題だと感じる(愛知県小学校)
▼本来の業務が減るわけではないので、勤務時間が倍増し、勤務時間外勤務が100時間を超えた(愛知県小学校)
▼校長も授業を持ち、教頭や教務主任などの持ち時数が大幅に増えた。人手不足で、職員室に人がいない。事務が出張のことも多く、職員室の留守番を1名置くのにとても苦労する。職員全体に余裕がなく、仕事を振れる教員がいない。余裕がないので、ミスも増え、それによりさらに仕事が増え、負のスパイラルになっている。児童一人一人に向き合う時間の確保が不可能に近いほど困難。行事などのために必要な会議や生徒指導のための緊急会議等、勤務時間内に会議を持つことが不可能であることが多い(埼玉県小学校)
▼支援学級2クラスを1人でみておられたので、児童への影響があった。教務教頭も対応したが、ただでさえかなりの超過勤務の役職なので、働き方改革どころではなかった(千葉県小学校)
毎月の残業時間が100時間以上、働き方改革どころではない、子どもたち一人ひとりと向き合う時間の確保も難しい……。学級崩壊を招いているとの声もありましたが、教員不足により一部では学校が学校ではなくなりつつあるのです。