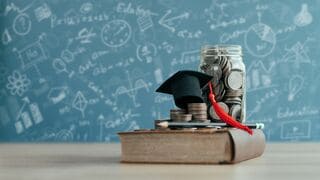一律月給の4%→10%以上でも「学校がもたない」
給特法が制定された1971年当時、1カ月の残業時間は8時間と見なすことが適正であるとの考えから、実際の残業時間に関わりなく、8時間の残業代に相当する額を支給する仕組みができたのです。
教員は放課後になっても翌日以降の授業の準備や採点、部活動の指導、各種報告書の作成、家庭との連絡調整などに追われ、多忙を極めます。児童・生徒を放りだして退勤するわけにもいきません。
そうした実態を受け、文科省に置かれている中央教育審議会(中教審)は、半世紀以上も前に決まった4%という水準を引き上げ、少なくとも10%以上にすべきだとの考え方をこの5月に打ち出しました。
ただ、教員側からは歓迎の声が上がる一方で、「残業時間に応じた手当が出るわけではない」「現場の忙しさに見合わない待遇」といった声も続出しました。
とくに「このままでは学校がもたない」と訴えてきた全日本教職員組合(全教)は中教審を厳しく批判。「長時間労働の解消のためには業務に見合った教職員の増員と業務量の削減が必要」とする声明を発表し、潤沢な予算を付けて教員を増やすよう要望したのです。
では、教員不足はどのような水準にあるのでしょうか。