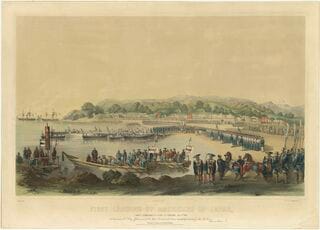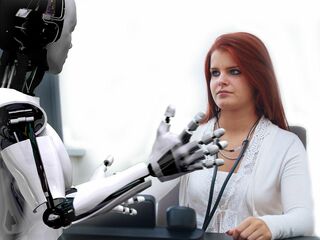ただし、石の華が見られるのは坑内の空気が乾燥している冬場から6月上旬ぐらいまで。石の華の季節が終わると、坑内は次第に湿気を帯びて、壁も足元もべしゃべしゃと濡れてくる。密閉された地下空間ではなく、ところどころに開口部があり、そこから外気が流れ込んでくるためだ。
 坑内には大きな開口部もあり、多少は外気も流れ込む
坑内には大きな開口部もあり、多少は外気も流れ込む
夏の盛りの暑い時期は、外気との気温差から薄い霞のようなものが漂い、ライトアップの光を受け幻想的な雰囲気となるらしい。季節を変えて再訪しても楽しめるのだ。
フランク・ロイド・ライトが着目
そもそも大谷石というのはどんなものか? 時を遡ること1500万~2000万年前、大規模な大陸変動が起こる中、マグマの熱や地底の圧力を受け火山灰などが固まったのが大谷石だ。薄い緑色の鉱物を含むことから、緑色凝灰岩とも呼ばれている。
他の石材に比べ軟らかく加工しやすいのが特徴の1つで、荒目(あらめ)という種類の大谷石はとくに耐火性に優れる。大正時代に米国人建築家フランク・ロイド・ライトが旧帝国ホテルの建材として利用し、関東大震災の火災にも耐えたことで、大谷石の名を世に知らしめた。現在もその特徴からピザ釜などに使われるという。
 大谷石の外壁。「ミソ」と呼ばれる茶色のシミが特徴の一つ
大谷石の外壁。「ミソ」と呼ばれる茶色のシミが特徴の一つ
以前は多くの採掘場があったが、2018年の時点で稼働しているのは5カ所とのこと。現在は細目(さいめ)と呼ばれる種類の、美観に優れた大谷石が、内装のインテリアなどに利用されることが多いようだ。
壁の筋には歴史が刻まれている
岩肌にある「筋」が場所によって違うことにも注目してほしい。これはどのように石を切り出したかを示す重要な手がかりなのだ。
この採掘場跡は1919年(大正8年)から1986年(昭和61年)までの67年間、実際に採掘が行われていた。最初の40年間、昭和34年頃までは、手掘りによる採掘だった。手掘りで切り出す石の標準的な大きさは15cm×30cm×90cmで「ごとお(五十石)」と呼ばれる。重さは約75kg。職人が1つの石を切り出すのにおよそ4000回もつるはしをふるったというから気の遠くなる話だ。
大谷石は、きれいな石の層とミソと呼ばれる茶色の塊が多く含まれる層がサンドイッチ状に重なっている。そこで効率よく採掘するために、まずは垣根掘りという横方向に掘り進めてきれいな石の層を見極め、その後に平場掘りという掘り方で下方向に掘っていく。天井近くの壁にある縦筋が垣根掘りの跡で、その下に平場掘りの横筋が続いている。
 平場掘りで刻まれた横筋は幅が15cm。切り出した五十石の幅と同じだ
平場掘りで刻まれた横筋は幅が15cm。切り出した五十石の幅と同じだ