EU大手術を訴えるマクロンに「パリ炎上」の冷や水
高級ブランド店の略奪まで正当化し始めたパリの破壊者集団
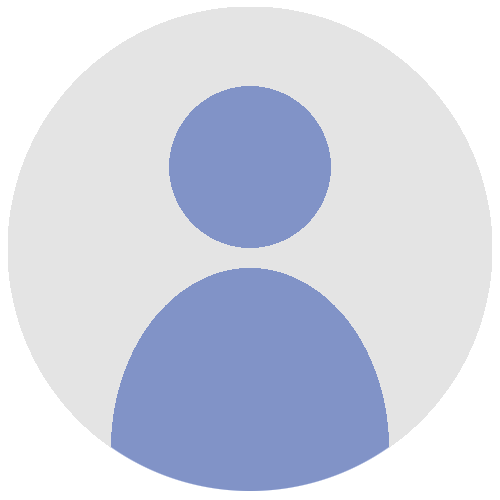
 著者フォロー
フォロー中
著者フォロー
フォロー中
2019.3.19(火)
住民対話も活発だった。税制、気候変動対策、民主主義といったテーマで議論が行われ、参加者の声はそのまま政府あての資料に記録された。抗議デモの引き金となった燃料税は「大きな航空会社から徴収すればいい」などの声が出た。「必需品を付加価値税(日本の消費税に相当。フランスでは価格の20%)の課税対象から除外して」「高級官僚や公務員の給料を公開せよ」「国の予算で運営されるテレビ局の記者たちはジャーナリストといえない。予算を減らせ」「警官の給料を引き上げて」などの声も強く、フランス人が共有する「平等」「社会正義」といった観念の健在ぶりも浮き彫りになった。
自らの国が抱える課題を近所で話し合う、民主主義の実践そのものだった。デモのスローガンに「指導者が国民から遊離している。マクロンは辞職せよ」という要求があったことを踏まえれば、政権が住民に政治参加の機会を提供したことは道理にかなっていた。
マクロン氏にとってのメリットも多かった。出張先まで大統領を追うメディアへの露出が増え、国民と語る姿をアピールできた。「力強いが尊大な男」との人物評がついて回る中、イメージアップの効果も多少あったはずだ。ネットを通じた政府への提案は、マクロン支持層の多くの人から回答が寄せられたことが世論調査会社の調べでわかっている。「対話」がマクロン氏の支持基盤を結束させる効果もあったといえるだろう。
問われる「成果」
だが、裏を返せば他政党への広がりには欠けたことを意味している。オランド前大統領を支えた社会党からはマクロン氏のメディアへの露出ぶりに「5月下旬の欧州議会選挙に備えた運動か」と皮肉る声が出た。「議員や労組代表の頭越しに有権者と直接取引している。民主主義の骨抜きだ」と嫉妬するような声も政界から上がった。さらに、多くの自治体で、参加者の大半が50歳代以上だったと報告されている。子育て世代や若者の声が吸い上げられたかどうかはわからない。
デモのそもそもの出発点は地方住民の「生活苦」だった。人々の台所の苦しさが解消したわけではない。支持率が多少回復しても、中間層の生活苦を改善する「成果」をもたらさない限り、抗議の火はくすぶり続ける。そんな認識を、地方自治体の多くの首長や国会議員らは抱いている。なかなか収束しないデモと、付随する暴力の拡散が、それを証明している。
炎上し、黒煙の上がるシャンゼリゼの16日の映像をスキー場で見たマクロン氏は、ツイッターに「さまざまな手を打ってきたが、まだやることがある。早い時期に再発防止のための強力な措置を取る」と書き込んだ。野党勢力が「政権の失態」を批判する中、翌17日には休暇を切り上げてパリへ戻り、フィリップ首相や担当閣僚らとの緊急対策会議に臨んだ。会議後、首相府は「16日の破壊行為を予測できず、暴力も封じられなかった。分析の結果、対策が十分でなかったことがわかった」との声明を出し、失策を認めざるを得なかった。政府は治安対策の強化に乗り出すが、仏メディアには、2カ月の対話行脚でマクロン氏は一定の地歩を築いたが、パリの炎によって「政局は元の鞘へ戻った」(ル・モンド紙)との辛辣な評価もある。
照準は欧州議会選へ
努力が水泡に帰すかのような事態の展開にマクロン氏は内心、苛立っているはずだ。目下の最大の懸案は、5月下旬にEU加盟国で一斉に行われる欧州議会選挙である。排外主義の極右やナショナリスト(国家主義)、あるいは権威主義体制を指向する政治勢力が「反EU」を掲げて各国で台頭しており、第2次大戦後の欧州で政治を動かしてきたキリスト教民主主義、社会民主主義、自由主義の既成主要政党が持っている議席を相当程度奪うとの懸念が強まっているためだ。





