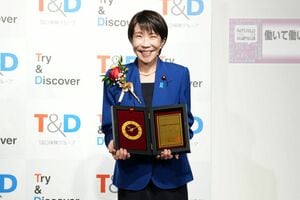これから日本企業が取り組むべき「ダイバーシティ3.0」とは?(写真はイメージ)
これから日本企業が取り組むべき「ダイバーシティ3.0」とは?(写真はイメージ)
多様な人材を活用するダイバーシティ(最近は「ダイバーシティ&インクルージョン」ともいう)の推進が政策的課題の1つになっている。女性、外国人、障害者など多様な人々が一緒に働ける職場をつくっていこうというわけである。それはまた年齢や就労形態、経歴などの多様化にもつながる。
しかし現状はダイバーシティで先進的とされる企業でさえ、せいぜい女性の管理職比率が何割になったとか、障害者を何パーセント雇用したという程度である。それも本音では法令や行政の指導でやむなく雇用しているか、企業イメージの向上が目的で行っているところが多い。
つまり「消極型」のダイバーシティであり、暗黙のうちにダイバーシティを経営の制約条件、あるいはコスト要因と位置づけている。
企業がダイバーシティに消極的なのは、そのメリットを十分理解していないためか、あるいはダイバーシティを推進するための制度的な条件(具体的にいえば個人の「分化」)が整っていないからである。
たしかに工業社会、とりわけ少品種大量生産全盛の時代には、人材の面でも均質性や画一性が求められた。個性や異質性は経営にとってどちらかというとマイナス要因だった。ところが生産システムの自動化やITの発達により、社員が同質でなければこなせないような仕事は大幅に減少した。逆にハードウエアよりソフトウエアが価値をもち、アイデアや創造性が求められるポスト工業社会では、個性や異質性こそが価値の源泉になる。