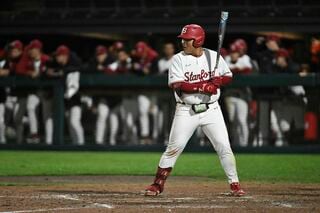多くのお雇い外国人の技術指導を通じ、鉄道敷設や架橋・築堤に関する技術が日本に伝えられたことによって、国内の鉄道網の整備が急速に進められた。
しかし、当時の日本が同時期に欧米諸国の支配下に置かれた他の被植民地諸国のようにお雇い外国人に全面的に依存するのではなく、あくまで日本が主体性を持って近代化政策の意思決定を下し、その主導権を譲ることがなかった点は特筆に価する。
当時の明治政府や関係組織の指導者たちが、大量にお雇い外国人を雇用し、技術を習得しながらも、どのように自主権を確立し、自立していったかについては、大阪産業大学経済学部で教鞭をとる林田治男教授の著書『日本の鉄道草創期明治初期における自主権確立の過程』(ミネルヴァ書房)に詳しい。
同氏は、鉄道分野のお雇い外国人の位置付けについて、史実を基に丹念に描写。当初は彼らの提案通りに結んでいた雇用契約を、次第に日本側が主導し条件提示するようになったことや、彼らが各組織のトップに就任することはなく、あくまで日本人上司の指揮命令系統に属していたこと、さらにそのポストも少しずつ日本人に代替されていった様子を明らかにしている。
 MR次官に対してグループ討議の結果を報告するMR職員(=JIC提供)
MR次官に対してグループ討議の結果を報告するMR職員(=JIC提供)
実際、日本政府が当時「雇って」いた外国人の数は、1874~75年が最も多かったが、その後減少し、1880年ごろには半減。さらにその後も減少し続けたとの推計もある。
こうして歩み続けた日本は、英国人技術者の指導によって新橋~横浜間で鉄道が開業されてわずか8年後の1880年に、外国人技師に頼ることなく日本人だけで初めて掘削を進めていた滋賀県と京都府の間の山岳隧道(逢坂山トンネル)を完工。
 講義後に現地メディアの取材に答える東さん(=同上)
講義後に現地メディアの取材に答える東さん(=同上)
さらに1893年には、日本初の国産機関車である860形も鉄道庁神戸工場で完成させている。
つまり、お雇い外国人は当時の日本にとって、確かに近代化に向けて歩む道しるべとしての役割を担ったものの、あくまで彼らは「日本人による鉄道建設・運営」という一貫した原則を支える助言者ないし脇役だったと言えよう。
それから約130年後の今日、日本は開発途上国の国々にとって重要な援助国としての地位にある。
かつてお雇い外国人から技術や知識を学び、急速に近代鉄道のネットワークを広げてきた日本が、いまや「質の高いインフラ輸出」や「官民連携」の高らかな掛け声の下、今度はその技術をミャンマーや多くの国々へ伝えるべく奮闘しているのは、隔世の感がある。
こうした中、日本のやり方を押し付けたり、自国の権益を優先し、利益の出る区間だけコンセッション契約で整備を進めたりするのではなく、時間がかかっても、ミャンマー人自身が自国の実態に即して自ら考え、行動に移すよう、地道な研修や改善提案などの側面支援に徹する東さんや松尾さん。その姿勢は、まさに日本自身の近代化の経験に根差したものだと言えるのではないか。
「日本からの支援は重要だが、MR自身がサービスの改善という課題を自覚し、それぞれの部署で取り組みを進めることが一番大切」だと東さんは強調する。かつて歩んだ道のりを、日本はどう先導していくのか。ミャンマー版お雇い外国人たちの奮闘は、まだまだ続く。
(つづく)