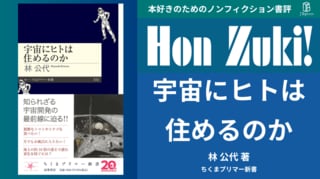週刊NY生活 2014年1月1日号472号
2014年1月17日で82歳。張りのある声で語るアートへの情熱は、半世紀前に日本初のモヒカン刈りで話題をさらった反骨精神あふれる若き日と同じ、いやもっと燃えたぎっている。
 篠原有司男さん
篠原有司男さん
ブルックリン・ダンボの自宅3階スタジオで、5メートル長の大作「歌舞伎マイケル・ジャクソン」を前に篠原さんが語る。マイケルが死んだときに「ほれぼれするようなやつ」と感動して、歌舞伎「鈴ヶ森」の白井権八に見立てた。10枚以上描いている。
「下絵はない。どんどん変えちゃう。僕の三原則は『早く、美しく、リズミカル』。早く描くってことは考えないってこと。人間は考えると、心地良い美しいものを描こうとしちゃう。それを意識的に壊さないと前に進んで行かないんだよ」
「60年代は日本の伝統くそくらえだった」という篠原さんは69年にロックフェラー三世基金の奨学金を得て渡米、ニューヨークに居を定め次第にアイデンティティを意識するようになった。
樋口一葉の『たけくらべ』をあえて汚い地下鉄の中やホットドック早食い大会の喧騒の脇で読んだ。「50回ぐらい読んだけど最後のページはもったいなくて読まなかったの。マクドナルドでバーガー食いながら読んだら涙が出たね」。センチメンタリズムを嫌う篠原さんが言う。
僕の原点と広げてくれたのは、国宝「鳥獣人物戯画」の巻物写本。最近は日本のコミックが頭から離れないとも言い、「口の中にも遠近法があるんだよ」と『名探偵コナン』初版本を開いた。
「『ワンピース』も1巻目を読んだとき、こいつはできると思ったね。発想とかめちゃくちゃ面白い」。感動したらスケッチブックに写し描きする。