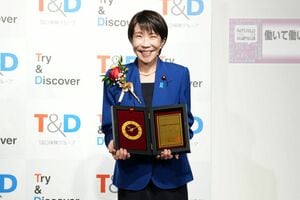昨日の「ハーバード・ビジネス・スクールはなぜ凄いか」では絶えず自己変革を起こすハーバード・ビジネス・スクール(以下、HBS)の一面を見ました。
その一方で日本の大学がなかなか変われないのは、リーダーや教員の危機意識が希薄なため構造自体が硬直化しているところにも問題があるようです。前稿に引き続き、HBS日本リサーチセンターの佐藤信雄所長に聞きました。
教える側の熱心さと努力が学生を変身させるHBS
HBSでは、テニュア(終身)教授になるまでには、博士号を取ってアシスタントプロフェッサーとして着任し、その後アソシエイトプロフェッサーからテニュアへというプロセスを経ますが、各段階に5~6年かかり、かつ昇進の際にはそれぞれ半数に絞られるシステムだそうです。
また、昇進するためには真剣にリサーチに努めることが必要とされるなど、日本とは異なる競争環境があります。しかも昇進にあたっては、その分野に詳しい教授に、審査される教員は世界で見てもトップに入るのか、ほかに良い教員はいるのかなどをヒアリングします。ですから、昇進をかける教員は自分の価値を実績として示さないといけません。
さらに、教育についても非常に熱心です。リサーチとティーチングの両方をしっかりやらないといけません。なぜそこまで熱心かというと、ケースディスカッションを通じて学生がどんどん変わっていくのを目の当たりにするので、先生にとっても面白味があるようです。これがレクチャー形式との大きな違いです。
HBSでは以前から「2年間でトランスフォーメーショナルな(変化が起きる)経験をさせますよ」と言っています。そこに昨年から実践的なフィールドワーク(FIELD、詳細は前稿参照)が加わったので学生はもっと変わると期待されています。
佐藤所長が、HBSに入って1~2カ月しか経っていない日本人の学生から実際に聞いた話によると、例えばレストランに入った途端に、その店のプロセスをつぶさに観察するようになったと言っていたそうです。
ここをこうした方がよい、これはこういう仕組みが働いているのだろうと、頭の中で瞬時に思考が働くようになったようです。それぐらい短期間で大きく思考回路を変える環境がHBSの特徴の1つなのでしょう。
レクチャー形式の場合、どうしても学んだことが学生の頭の中に残りづらいですが、ケーススタディを通じて学んだことは血となり肉となるわけです。しかもディスカッション形式なので、人によって様々な考えがあることに気づきます。
正解でなくても、その状況での「最適な解」を導き出す訓練を受けることが個々人のポテンシャルを引き出す結果につながります。
1クラス90人の多様な考え方に触れて、こんな角度から考えられるのか、こう考えないといけないのか、自分はこういうことは普段考えていなかったなど、多面的な見方が身につきます。こうしたことを1人の教員が与えるには限界があります。
しかし教員からすると、予定調和的なレクチャー形式に比べ、想定外の質問や反応にも柔軟かつ適切に対応しなければならない生のケースディスカッション形式は非常に負担がかかるのではないでしょうか。佐藤所長によると、教員は相当な準備をしているようです。