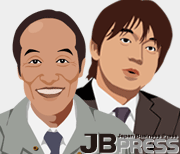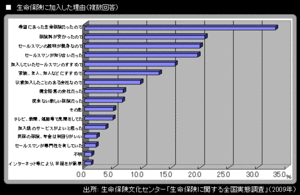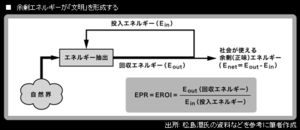日本でも、経済産業省の主導で、官民一体で取り組みを進める推進母体として「スマートコミュニティ・アライアンス」が2010年4月に発足した。京都府・大阪府・奈良県にまたがる「けいはんな学研都市」(関西文化学術研究都市)、福岡県北九州市、愛知県豊田市、横浜市をスマートコミュニティ国内実証地域に選定した。
「スマートシティ」の取り組みは先進国だけでなく、中国やブラジルなど新興国でも始まっている。既存のインフラを引きずっている先進国の都市に対し、新興国は後発者利益を最大限に活用して、最先端のスマートな社会インフラを一挙に構築することを目指している。電力だけでなく、鉄道、水道、空港、港湾などの社会インフラの構築が同時並行して進められるため、100兆円を超える市場規模が推定されている。
今後の日本の展開
日本政府はこうした動きを見越して、インド国内の鉄道事業への資金援助と引き換えに、インド政府が計画中のスマートグリッド整備事業の優先交渉権を獲得した。鉄道を敷設するデリーとムンバイの間の4都市で、スマートグリッドのほか、上下水処理や公共運輸システムなど、都市インフラの一体開発に着手する。2011年にも日本企業約10社が参加して実証実験をスタート、その結果を踏まえて事業化するとしている。
インドでの事業を通じてスマートグリッドやスマートコミュニティ構築のデータとノウハウを蓄積し、これを足がかりに中国や東南アジア地域でもプロジェクト受注を目指すのが、日本政府の狙いだ。
米ネバダ州の空軍基地に設置された太陽光パネル〔AFPBB News〕
「スマートシティ」「スマートコミュニティ」プロジェクトの特徴の1つは、従来の情報化のように米国のモデルを各国がそのまま模倣するわけではないということだ。
かつては米国が情報化のトップランナーであり、世界各国は「アメリカに追いつけ、追い越せ」とばかりに米国が進んだ道をトレースして技術を進化させ、米国と同じような情報社会を目指してきた。
しかし、インターネットが世界的に普及し、グローバリゼーションが国際サプライチェーンを作り出し、世界が1つのグローバル経済体制となっていく過程で、途上国・新興国は米国とは違うルートで情報化を進めている。
多くの新興国では、固定電話が普及する前に携帯電話が普及した。情報化の進み方は、先進国と新興国では異なっている〔AFPBB News〕
例えば、情報社会の基盤である電話網においても、多くの途上国では、有線の固定電話網が普及する前に都市部を中心に携帯電話が普及し、無線方式によるインターネット接続が実現した。先進国では、まず固定電話時代が長く続き、その後インターネット利用の広がりに合わせてADSLや光ファイバーによるブロードバンド化が進み、携帯電話の普及が同時進行したことを考えると、先進国と途上国では情報社会のあり様が異なることは明らかである。
情報社会を規定する要因は、主に次の3つだ。第1は、技術的要因・技術合理性。第2は、グローバル化、国際競争からの規定要因。第3は、各国民国家の持つ歴史的社会的要因・近代化との相関。この3要因のベクトルの合計として、それぞれの国の情報社会の方向性が決まっていく。
日本の情報化もこの3要因から成り立っていると考えれば、日本のやり方がそのまま新興国や途上国に適合する面とそうでない面とを持ち合わせていることは自明である。
むしろ、日本が今後中国や東南アジアのスマート化を担っていくには、まず相手国の社会的歴史的状況をよく理解し、相手の価値観を尊重して、日本流を押し付けるのではなく柔軟性を持った対応ができるかに掛かっている。