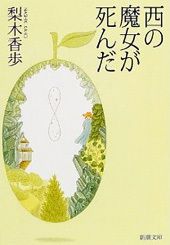2008年に映画化された『西の魔女が死んだ』は、児童文学者でもある著者の代表作の1つで、中学生の少女・まいの成長物語。「西の魔女」とはまいの祖母のことで、日本人の祖父と結婚して日本に住み着いた英国人女性。登校拒否となったまいは、田舎に住む祖母に預けられる。
都会とは全く異なる環境で、静かに、毅然として、心豊かに生きる祖母。まいは祖母のもとで、規則正しく暮らすこと、自分の考えをしっかりと持つことを学んでいく。タイトル通り、祖母は死んでしまうが、でも、まいの中には、しっかりと祖母の記憶と祖母から学んだことが刻まれる。15年以上前の作品だが、今も、読み続けられるロングセラーだ。
しかし、そんな初々しい時期が思い出せないぐらい昔に過ぎ去ってしまった私にとっては、「西の魔女が死んだ」は少々、美しすぎて、現実感に乏しいストーリーのように思えた。
だから『春になったら苺を摘みに』という、いかにも女の子が好きそうなお伽噺のようなタイトルに身構えてしまった。またしても、私が思い出すことができない「感覚」が描かれているのではないのと・・・。
しかし、そんな心配は杞憂だった。ふわふわとしたタイトルとは裏腹に、現代的で、切実な、大人の感覚が溢れていた。
著者が英国に留学していた頃の暮らしぶりや、イギリスを再訪した時のことを綴ったエッセイ集。特に、下宿の女主人・ウェスト夫人との交流を中心に描かれている。
ウェスト夫人は信仰心が篤く、人情味溢れる人だ。面倒だと分かっていながら面倒ごとを引き受けてしまう。犯罪歴のある人、考えが違う人も下宿人として受け入れる。近所の嫌われ者も見捨てることができない。そこでぶつかったり、時によっては不快な思いをしたり、傷ついたりする。それでも、ウェスト夫人は自分のやり方を変えることはしない。
最初は、昔堅気のご婦人の日々の暮らしを切り取った日常雑感のように読み流していた。しかし、読み進むにつれ、ウェスト夫人は「人間と人間が繋がっていること」の象徴として存在感を増してくる。
人と人が接点を持つというのは、恐ろしく面倒なことだ。生まれ育った環境も違えば、どんな教育を受けたのか、信じている宗教も違えば、勤めている会社も違う、経済力も異なる。何もかもが違う者同士が分かり合うことは、それほど簡単なことではない。時にはぶつかり、傷つき、妬み、憎むこともある。
しかし、そういうプロセスを経てこそ、次のステップに進めるのだ。もしかしたら、永遠に理解し合うことはないかもしれないけれど、相手を尊重できるようになるかもしれない。
インターネットが普及したお陰で、私たちはバーチャルの世界の中でたくさんの人と出会うことができるようになった。遠い国の人とも情報を共有したり、感動を伝え合うこともできる。インターネットは便利で楽しいことを私たちにたくさん与えてくれる。
でも、本当に人と人が繋がるということは、もっと手間ひまがかかり、面倒臭くて、疲れること。それでも、誰かと繋がっていなければ生きていくことができない──そんな人としての原点に立ち返らせてくれるエッセイだ。
恐らくは、著者が一番伝えたかったであろう一節が心に突き刺さった。
そうだ
共感してもらいたい
つながっていたい
分かり合いたい
うちとけたい
納得したい
私たちは
本当は
みな
その切実な思いに、心から共感できた。