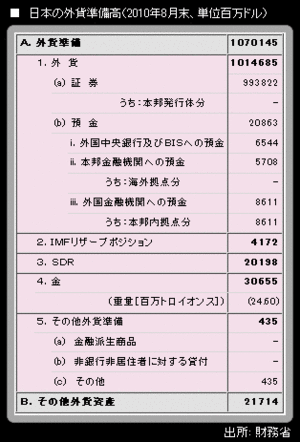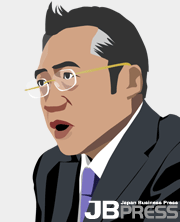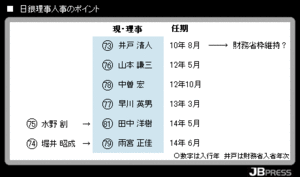金融政策はバブルを予防すべきか、否か。
米連邦準備制度理事会(FRB)を筆頭に、世界の中央銀行の間では「放置論」が主流だった。しかし、2008年9月のリーマン・ショック以降、世界経済が同時不況に直面すると、その潮流が変わり始めた。
金融政策運営において、バブルは厄介な存在である。株式や不動産など資産価格の膨張は、景気の振幅に大きな影響を与える。しかし、資産価格を金融政策の直接的なターゲットにするのは現実的でない。そもそも、バブルを認識することは極めて難しい。
「放置論」はこうした現実を受け入れ、「バブルが崩壊したら、直ちに利下げして対処すればよい」という受け身型だ。バブル予防を重視するあまり、過度な引き締め(利上げ)で景気を冷え込ませれば批判を浴びかねない。一気に利下げすれば、あるいは流動性を大量供給すれば、危機は回避可能だという思い込みもあったのだろう。
バブルは予防できるのか〔AFPBB News〕
これに対し、「予防論」は受身的な立場から一歩踏み出す。金融政策運営の軸足をやや資産価格の側に置き、一般物価に影響を及ぼす前から政策対応すべきだという発想になる。
国際決済銀行(BIS)のホワイト前金融経済局長は熱心に予防論を展開し、同氏と個人的にも親しい日銀の白川方明総裁も予防論者に名を連ねる。日銀の場合、1980年代後半のバブルの後遺症に長く苦しんだ経験も背景にある。
戦犯FRB、バブル予防論に傾斜
予防論に宗旨変え?〔AFPBB News〕
「中央銀行は資産価格がバブル化して大問題を招く前に行動すべきか。ごく最近まで、この問いに対して多くの中央銀行が『ノー』と答えていた。金融政策はバブルの最中でもインフレや雇用に焦点を当てるべきと考えられていたし、私もそう思っていた。しかし、今回のバブル崩壊が悲惨な状態をもたらした今、別な視点で考える必要があると思う」
サンフランシスコ連銀のイエレン総裁は4月16日の講演で「予防論」への宗旨変えを示唆した。
イエレン総裁は、金融政策の舵取りを決める連邦公開市場委員会(FOMC)の古参メンバーの1人。発言は個人的な見解に過ぎないとはいえ、放置論の総本山であったFRBでもバブル予防の必要性が意識されつつあることの証左だ。
リーマン・ショック後のFRBの果敢な利下げは奏功せず、受け身型対応の限界を露呈した。もとより、今回のバブルのA級戦犯と見なされているFRBに対しては国民からの批判が根強く、予防論に傾斜せざるを得ないという事情がある。