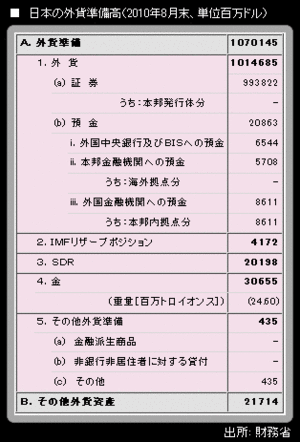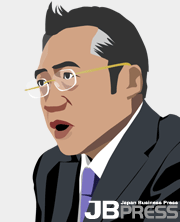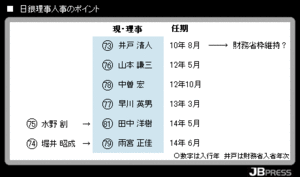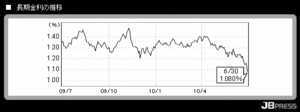外為市場で円高が進展し、円売り介入と金融緩和の同時実施を求める大合唱が始まった。
 金融緩和の追加を決めた白川方明日銀総裁
金融緩和の追加を決めた白川方明日銀総裁
2009年6月12日の当コラムで、筆者は「日銀が『TOKYO連銀』になる日=ドル安志向に傾く米国」と論評した。やはりと言うべきか、金融・財政の発動余地が乏しい米国はドル安への依存姿勢を強めた。一方、日銀は2010年8月30日、介入に先立って金融緩和の追加を決定し、「TOKYO連銀」に向けて第一歩を踏み出した。
今回の円高では、米連邦準備制度理事会(FRB)の「緩和的措置」が引き金になった。FRBが2010年8月10日の連邦公開市場委員会(FOMC)で国債買い入れを決定すると、これが金融市場では「事実上の金融緩和」(外資系証券)と受け止められたのだ。
厳密に言えば、この措置は金融緩和ではない。FRBが過去に買い入れた住宅ローン担保証券(MBS)のうち、償還が到来する分を国債に乗り換えるだけだからだ。買い入れたMBSと国債の合計資産に変化はなく、MBSが減少する分、国債が増える形となる。つまり、MBSから国債への乗り換えがその実態である。
とはいうものの、金融市場がこれを「緩和」と見なして為替相場がドル安・円高に振れると、日銀は対抗上緩和せざるを得ない状況に追い込まれる。
すなわち、日米の中央銀行が何をやろうとも、「日本は緩和度合いが弱い」という印象が円高をもたらす限り、日銀はFRBへの追随を迫られる。その意味では、今回の緩和は典型的な「TOKYO連銀化」のパターンにはまった格好だ。
カギ握る米金利動向は「典型的なデフレパターン」
今後の展開はどうなるのか。そのカギを米経済のファンダメンタルズ(基礎的条件)が握っている。これまでは回復傾向を示していたが、ここにきて雇用情勢の改善が足踏みし、住宅市場もなお底入れが見えてこない。金融市場では、「二番底の懸念がある」(別の外資系証券)との見方が広がっている。