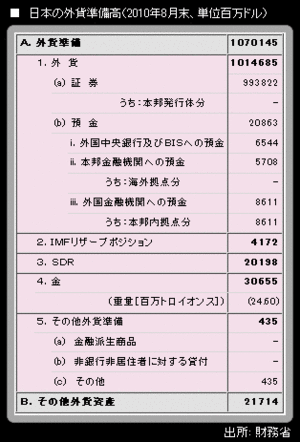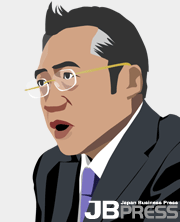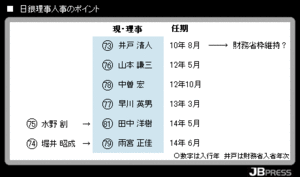では、バブルは予防できるのか。
イエレン総裁は予防論の限界にも言及している。主な論点を紹介しよう。
(1)株価の引き締めは、株高による総需要の増加を打ち消す程度に限定されるべきだ。金融政策は株高に反応するのではなく、株高がマクロ経済に与える影響に限って対応する必要がある。
(2)経済ファンダメンタルズの推計は不正確で、バブルの捕捉は容易ではない。このため、政策当局者が効果的に行動する時期を正しく認識できるかどうかは疑問だ。
(3)バブルは金融政策が早急に対処するほど深刻なものか。政策当局は、バブルの影響が極めて深刻になる可能性が高い場合に限って行動すべきだが、バブル生成・崩壊の影響はかなり時間を経て徐々にしか表面化しないこともある。
(4)危険なバブルが察知でき、それを抑制する行動が正当化されるとしても、金融政策での対応が最良のアプローチではないかもしれない。金融政策と資産価格・信用市場などの相関性には論議の余地があり、利上げに対して予測通りの反応を示さない可能性がある。
景気回復優先なら、バブル再燃も
筋金入りの予防論者である白川総裁でさえ、4月23日にニューヨークで行った講演でバブル制御の難しさを認めている。
筋金入りのバブル予防論者〔AFPBB News〕
この中で、白川総裁は「中央銀行はバブルを予防することと、バブルの崩壊の影響を緩和することの双方に注意を払うべきだ」と強調しながらも、「バブルの生成の認識が困難であると同時に、破裂しつつある時ですら、それに気づくことは難しい」と語った。予防しようにも、バブルかどうかは正確には分からず、崩壊もすぐには認識できない。とすれば、金融政策では適切に対処できない公算が大きくなる。
中央銀行が資産価格を抑制する場合、「中央銀行は資産市場より将来の予測能力が高い」という前提条件が必要となる。株価は経済の先行指標であり、中央銀行もその動向を参考にする存在。つまり、バブルの予防に努めるのなら、「株価が間違っている」と判断できるほどの分析能力を高めなくてはならない。
言うまでもなく、「金融政策だけでバブルの生成・崩壊の再発を回避できるものではない」(白川総裁)。世界的なバブル崩壊という悲劇を再び繰り返さないためには、金融システムの監視体制やリスク管理の在り方なども洗練化する努力が求められる。
その成果が問われるのは、景気が本格回復する局面だ。各国中銀は恐慌を回避しようと非伝統的領域に突入しているが、景気回復を重視するあまりに「出口政策」が遅れると、次のバブルが発生しかねない。
その一方で、バブル再燃を恐れて出口が早過ぎれば、不況に逆戻りするリスクがある。適切なタイミングで出口政策に着手できなければ、バブル予防の金融政策は絵に描いた餅で終わるだろう。