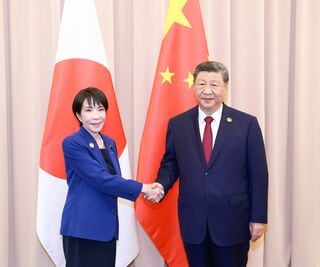地政学リスクの高まりで問われる「責任ある撤退」
紛争地域・高リスク地域における企業の人権対応に関するセッションでは、「深刻な人権侵害が続き、情報が錯綜する中、企業や投資家はいつどのように事業から手を引くべき
残り4389文字
紛争地域・高リスク地域における企業の人権対応に関するセッションでは、「深刻な人権侵害が続き、情報が錯綜する中、企業や投資家はいつどのように事業から手を引くべき
残り4389文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら