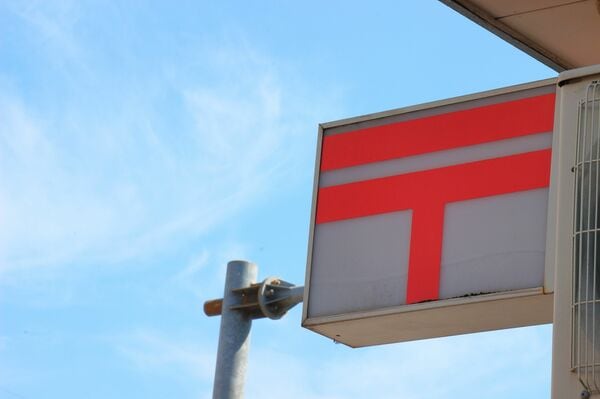 「ブラック企業」顔負けの郵便局(写真:HiLens/イメージマート)
「ブラック企業」顔負けの郵便局(写真:HiLens/イメージマート)
郵便局の不祥事や問題が次々と報告されている。郵便局の問題を報じてきた西日本新聞には、被害者の悲鳴や郵便局の内部告発が対応しきれないほど舞い込むようになったという。『ブラック郵便局』(新潮社)を上梓した西日本新聞記者の宮崎拓朗氏に聞いた。(聞き手:長野光、ビデオジャーナリスト)
──郵便局による、高齢者をターゲットにした、極めて強引で時に不正も混じる保険の勧誘について書かれています。
宮崎拓朗氏(以下、宮崎):私が取材した中で最も悪質だと感じたのは、山口県の30代の男性のケースです。保険の契約をしたのは軽度の認知症を持つ男性の母親で、母親の家を郵便局員が何度も訪問し、繰り返し不必要な保険の契約を結ばせていたのです。
男性が母親に保険について聞いても「郵便局の人に任せているから」と答えるばかりで、本人は何も理解していませんでした。家の中を調べると、次々と保険の契約書が見つかり、1年間で11件もの保険の契約を結ばされていました。
1カ月で5件も新しい契約をさせられていた月もありました。母親の口座からは1年間で200万円以上の保険料の支払いがあり、ついに貯金残高はゼロになっていました。
高齢の方が不必要な契約を結ばされ、その子どもが異常に気づいて声を上げるケースを他にも複数取材しました。こうした問題の背景には、郵便局員に課せられた厳しい保険契約のノルマがあったと思います。
郵便局員に取材をすると、ノルマが達成できないと研修会に呼び出されてつるし上げられたり、土下座を強要されたりするといった実態が明らかになりました。「厳しい圧力に耐えかねてお客さまを騙してしまった」と涙を流しながら告白する郵便局員もいました。
また、一部ではありますが、基本給とは別の営業手当が目的で、不適切な営業を繰り返して、かなり稼いでいた局員がいたことも事実です。
──「乗り換え契約」や「2年話法」といった巧妙な保険契約についても書かれています。
宮崎:「乗り換え契約」とは、古い保険を解約して新しい保険に入り直すことです。
世の中の情勢や加入者のライフスタイルの変化によって必要な保険が変わることもありますから、客が望むのであれば乗り換えることには何も問題はありません。ただ、保険の乗り換えには、解約による損失や保険料の値上がりなどのデメリットが伴うことがあります。
当時の郵便局では、局員が営業実績を稼ぐために、こうしたデメリットを十分に説明しないで乗り換えを勧めるケースが相次いでいました。新しい客を見つけるのは手間なので、既存の客に営業することで手っ取り早く契約を結んで営業ノルマを達成したいという郵便局員側の事情がありました。
















