大河ドラマ『べらぼう』田沼意次を蝦夷地の開発へと駆り立てた日本初のロシア研究書『赤蝦夷風説考』とは?
2025.6.7(土)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
大河ドラマ『べらぼう』「1200両で身請けされた花魁・誰袖」と「“春町文字”を生み出した恋川春町」の意外な末路

あわせてお読みください
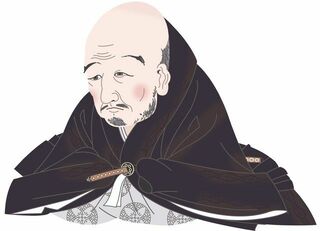
大河ドラマ『べらぼう』葡萄酒を傾ける薩摩藩主・島津重豪の人物像、一橋治済の策略に加担する巧みなストーリー展開
真山 知幸

美人画の歌麿、役者絵の写楽、スペクタクルな国芳、世界的巨匠の北斎と広重、浮世絵の黄金期を築いた5人が夢の競演
東京・上野の森美術館で「五大浮世絵師展―歌麿 写楽 北斎 広重 国芳」が開幕
川岸 徹

銃で日本を脅した米国より紳士的だったロシア
詳説:北方領土問題と日本・ロシアの近代史
杉浦 敏広
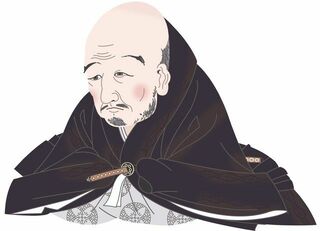
大河ドラマ『べらぼう』葡萄酒を傾ける薩摩藩主・島津重豪の人物像、一橋治済の策略に加担する巧みなストーリー展開
真山 知幸
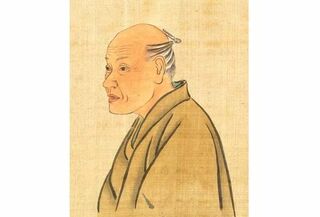
『べらぼう』江戸随一の文化人・大田南畝の生涯、狂歌の基盤は幼少の学問から、『寝惚先生文集』で人気、意外な晩年
蔦重とゆかりの人々(20)
鷹橋 忍
本日の新着

「中国が『EUV露光装置』試作機完成」の衝撃…世界の半導体秩序は抜本的に書き換えられてしまうのか?
莫大なカネとヒトをつぎ込んだファーウェイ、中国半導体版「マンハッタン計画」の行方
湯之上 隆

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常
【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】
若月 澪子

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力
身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点
市ノ瀬 雅人

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択
大谷 達也
豊かに生きる バックナンバー

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択
大谷 達也

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性
川岸 徹

姫路城を築いた池田輝政によって近世城郭に整えられた吉田城、一見地味でも何かと面白い要衝の地にある城
西股 総生

大河ドラマ『豊臣兄弟!』第1回で描かれた秀長の本質、兄・秀吉の帰還で動き出す運命──史実の空白をどう埋めた?
真山 知幸

若き曹操を乱世の奸雄にした分岐点、運命が切り替わった理由と混乱期に飛躍する人の共通点
鈴木 博毅

住宅ローンは絶対に繰り上げ返済してはいけない!金利上昇であわてて返済したら大損する理由を合理的に解説
我妻 佳祐



