ようやく「同じ目線に」…羽生結弦が野村萬斎との共演で見せた覚悟、そして3.11被災地への鎮魂と祈り
アイスショー「ノッテ・ステラータ」レポート(1)
2025.3.10(月)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
羽生結弦を驚愕させた野村萬斎の「器」…狂言とアイススケートの完璧なコラボ実現へ2人の徹底したこだわりとは

あわせてお読みください

羽生結弦を驚愕させた野村萬斎の「器」…狂言とアイススケートの完璧なコラボ実現へ2人の徹底したこだわりとは
アイスショー「ノッテ・ステラータ」レポート(2)
田中 充

羽生結弦さん「最近は孤独を感じない」…感極まった孤高のスケーターはなぜ、そう打ち明けたのか
【詳報】「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」千秋楽(2)
田中 充

羽生結弦さんが見せた執念と闘争心、単独公演で5年ぶりに蘇らせた伝説のプログラム…暗闇のリンクに浮かんだ姿とは
【詳報】「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」千秋楽(1)
田中 充

【詳報:羽生結弦、30歳の舞②】“推し”に圧倒的な“おもてなし”…単独公演の醍醐味はエンディングから始まる
田中 充

【詳報:羽生結弦、30歳の舞①】「命」の物語を自らつづり、滑る理由…プロスケーターとして到達した哲学的境地とは
田中 充
本日の新着
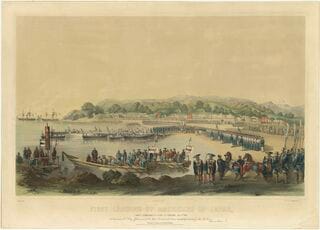
哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質
幕末維新史探訪2026(2)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語②
町田 明広

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか
【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略
小林 啓倫

でっち上げた疑惑でパウエル議長を刑事捜査、トランプの狙いは「FRBの隷属」、中央銀行の独立性をいとも簡単に蹂躙
木村 正人
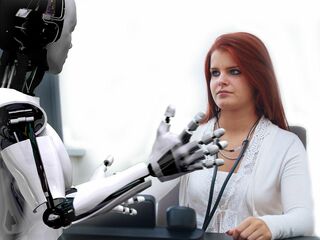
AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影
生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に
小久保 重信
スポーツの見方・勝ち方 バックナンバー

トランプ政権のマドゥロ拘束で「WBC」と「サッカーW杯」の開催も視界不良に、…国際大会に忍び寄る「国家暴走」の影
臼北 信行

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に
広尾 晃

「流れを変えるだけの戦力がなかった」 箱根駅伝、“21年連続シード”を逃した東洋大に何が起きたのか?
酒井 政人
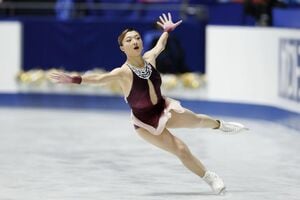
坂本花織の「五輪ラストダンス」、大技なしの女王が築いた“新しい成功モデル”の全貌に迫る
砂田 明子

箱根駅伝V候補が王者・青学大に大きく離された理由とは?全日本1位の駒大はエースが走るも6位、同2位の中大は5位
酒井 政人

なぜ大相撲だけが視聴率20%を取れるのか?WBC・W杯以外は苦戦する地上波スポーツ中継で相撲が勝つ構造的強さ
長山 聡



