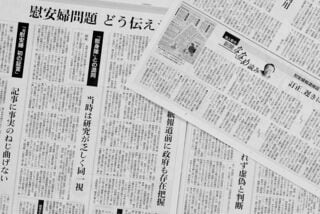新年一般参賀に臨む天皇陛下と皇后雅子さま(写真:代表撮影/ロイター/アフロ)
新年一般参賀に臨む天皇陛下と皇后雅子さま(写真:代表撮影/ロイター/アフロ)
皇籍離脱した小室眞子さんの米国での生活、悠仁親王の大学受験に愛子内親王、佳子内親王の結婚相手候補。皇室を巡る話題は後を絶たず、我々一般人のお茶の間を賑やかすコンテンツの一つになっている。
明治時代からメディアは皇室報道に力を入れてきた。その報道も、「権威」に重きを置く時代もあれば、消費的な内容となる時代もあった。皇室報道はどのように変化してきたのか、現在の皇室報道の問題点、そして今後の皇室報道の在り方とは──。『皇室とメディア 「権威」と「消費」をめぐる一五〇年史』(新潮社)を上梓した河西秀哉氏(名古屋大学大学院人文学研究科准教授)に話を聞いた。(聞き手:関瑶子、ライター&ビデオクリエイター)
──昨今の皇室報道は、一方的なバッシングのようなものが多くなっているように感じられます。なぜこのような状態になってしまったのでしょうか。
河西秀哉氏(以下、河西):昭和の時代、報道機関の皇室記者は、長くその職に就いている人がほとんどでした。
例えば、当時の皇太子と皇太子妃(現在の上皇ご夫妻)は、非公開の記者会見の機会を多く設けていました。その場には、皇室報道一筋何十年という記者が勢揃いし、かなり厳しい質疑をしていたようです。
「今の回答はおかしいのではないか」「皇太子はこうあるべきではないか」など、提言めいた意見に対しても即座に答えなければならず、そういった記者たちとのやり取りを通して自己表現力が磨かれていったと思われます。
ところが、今では報道機関の皇室担当記者はローテーションで次々に変わるため、宮内庁や皇室の立場をじっくり考えさせるような難しい質問をするよりも、無難なものになっています。半面、週刊誌やテレビのワイドショーなどは刹那的に、消費的に皇室を扱うようになりました。
その場その場で盛り上がって雑誌が売れればいい、視聴率が稼げればいいという方向にメディアが変わってきたのです。
平成に入ってから、だんだんと皇室が我々一般人に近付いてきているようになったと感じている人も多いかと思います。それは、テレビではニュースではなくワイドショーが、活字では新聞ではなく週刊誌が皇室報道の媒体として私たちの生活に入り込むようになったためです。
ワイドショーや週刊誌は、ややともすると下世話とも言える内容の皇室報道をすることがあります。それが一般の人たちの受けがいいとなり、報道の内容がどんどん過激になっていったのです。
──そのようなメディアの報道の仕方を、皇族はどのように思っているのでしょうか。
河西:あくまでも私の推測ですが、よしとしていない部分はあるにせよ、ある程度は許容しているのではないかと思います。