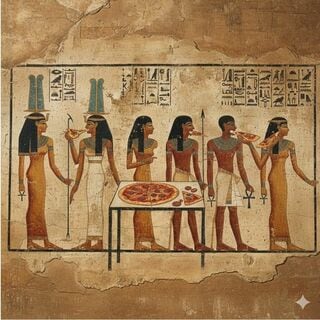『監督の財産』に収録された「2 覚悟」を綴った当時・監督就任1年目の栗山英樹氏。写真:高須力
『監督の財産』に収録された「2 覚悟」を綴った当時・監督就任1年目の栗山英樹氏。写真:高須力
侍ジャパンの監督として2023WBCで世界一を奪還、大谷翔平の二刀流を押しすすめ、ファイターズの監督としては歴代1位の勝利数を積み重ねた。
不可能と思えることを可能にしてきた指揮官・栗山英樹。
約12年の監督生活で知り得た「経験知」を後世に遺したい――そんな思いが結集した一冊は、『監督の財産』と題されて9月9日に刊行される。
「監督と選手」「監督と人事」「監督の役割」など、監督という仕事に必要だった知識から、大谷翔平、近藤健介、中田翔らスター選手とどう接し、彼らから何を学んだか、その秘話までを余すことなく綴った「監督としての集大成」となっている。
その『監督の財産』の一部を紹介。今回は「1年目、監督就任したシーズンオフ」に綴った「新米監督の思い」。
【関連】「監督の財産とはどんな本なのか」
「野球人として、こんなに幸せなことはない」
(『監督の財産』収録「2 覚悟」より。執筆は2012年)
今年(※編集部注・2012年)、はじめて監督を経験して、何が一番の衝撃だったかといえば、プロ野球という存在そのものが衝撃だった。
毎日が苦しい。一日中苦しい。
長年、それを伝える立場にあったはずなのに、本当の現場の苦しさを、僕はまるで分かっていなかった。いまになってプロ野球という戦いの厳しさに衝撃を受けている。
北海道日本ハムファイターズの監督に就任して1年目。正直、これほどのつば競り合いを経験できるとは思っていなかった。
読売ジャイアンツが早々とセ・リーグ優勝を決めた9月21日、ファイターズはパ・リーグの首位に立っていたが、2位の埼玉西武ライオンズとは1・5ゲーム差、3位の福岡ソフトバンクホークスとは4ゲーム差という、熾烈な優勝争いの真っ只中にいた。
 監督1年目、優勝争いを繰り広げていたときの栗山英樹氏(2012年撮影:高須力)
監督1年目、優勝争いを繰り広げていたときの栗山英樹氏(2012年撮影:高須力)
人生50年、いまほど必死になったことはない。現役時代は必死じゃなかったのかというと決してそんなことはないが、間違いなくあの頃よりも、いまのほうがはるかに必死だ。あの頃も命がけだったけれど、いまはもっと命がけ。毎日、命を削っているという実感がある。
本当に出し尽くしている感じがあるから、ここまで出し尽くして最後に負けたんじゃなんにも残らない、そんな思いもふつふつと湧いてくる。
結局、リーグ優勝をするか、それとも日本シリーズを制するか、そのどちらかしか意味がないのだ。
長いシーズンを戦っていると、どうにも流れが悪いときというのは必ずある。そんなときは、何をやってもうまくいかないものだ。何か手を打たなくては、とは思うのだが、実は手の打ちようというのはそんなにない。
打線がつながらなければ、もちろん打順の組み替えも考えるけれど、我々は一番良いと思って打順を組んでいるわけだから、わざわざ奇をてらっても仕方がない。
そういうときが一番きつい。
何をやってもダメなときは、ひたすら我慢するしかなくて、毎日、すり減ってしまう感じがする。しかも、監督がすり減るということは、選手たちはもっとすり減っているということなのだ。
 9月9日に発売される『監督の財産』(栗山英樹著)
9月9日に発売される『監督の財産』(栗山英樹著)
ベンチにいる僕の顔がよっぽどやつれて見えるのか、知人にはいつも体調を心配されたが、試合中にクラッとくるようなことはない。試合中は完全にケモノに戻っているような感じで、試合が終わっても、その日のうちは興奮しているから疲れは感じない。
一番疲れを感じるのは、寝て、次の日の午前中。寝ることで一回断ち切られて、疲れを感じる。ただ、やっぱり監督は一番元気でなくてはいけないから、人前に出るときはテンションを上げる。
もしかするとそれが一番しんどいかもしれない。本当は疲れているのにテンションを上げなければならない、そのスイッチを入れる瞬間がとにかくしんどいのだ。
2003年、阪神タイガースを18年ぶりのリーグ優勝に導いた星野仙一監督(現・東北楽天ゴールデンイーグルス監督)が、胴上げ直後の優勝監督インタビューで発した第一声が、「ああ、しんどかった」だった。あのときは想像することしかできなかったけれど、いまは実感が伴う。
ただ、毎日しんどいばかりじゃ体がもたないので、いまは、「この時期まで優勝争いができるなんて、こんな面白いことはない」と思うようにしている。「野球人として、こんなに幸せなことはない」そう思い直してから、少し眠れるようになってきた。
(『監督の財産』収録「2 覚悟」より)