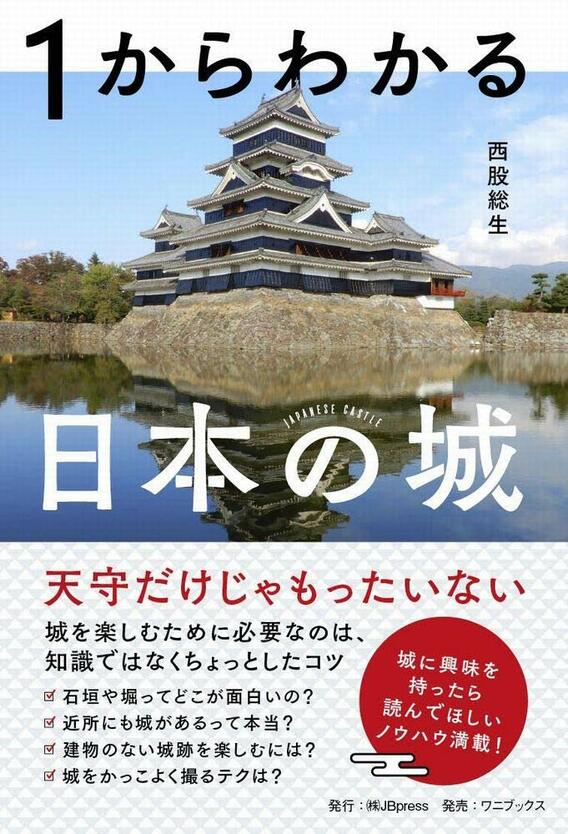江戸城天守台 撮影/西股 総生(以下同)
江戸城天守台 撮影/西股 総生(以下同)
(歴史ライター:西股 総生)
「家臣思いのありがたい殿様」だったのか
徳川幕府の正史として編まれた『徳川実紀』という史料がある。この史料によれば、家康が江戸城に入城したのは1590年(天正18)8月1日で、本多正信と榊原康政が城の内外を案内している。城はすでに徳川軍の接収下にあったから、正信・康政が一足先に江戸に入って、家康を迎える準備を進めていたのだろう。
『徳川実紀』が伝えるところによると、城内の古屋はどれも田舎風で玄関も粗末な造りだった。正信が「他はともかく、この玄関はあまりに見苦しい、他国の使者を迎えることもあるでしょうから、ここだけは造作しましょう」と進言したが、家康は笑って取り合わなかった、という。
 山中城(静岡県)にある〝戦国風〟の休憩舎(イメージ)
山中城(静岡県)にある〝戦国風〟の休憩舎(イメージ)
なかなかありそうな話で、大河ドラマの配役でこのシーンを見たい気がする(笑)。このくだりを読むと、たしかに江戸城はボロ城として語られている。つづけて『徳川実紀』は、次のようなエピソードを記す。
家康は、城の普請は本丸と二ノ丸の間の空堀を埋める程度で済ませ、代わりに家臣たちの知行割当てや屋敷割を進めていった、と。
 江戸城の天守台から見た本丸。家康は北条時代の堀を埋めて本丸を拡張していった
江戸城の天守台から見た本丸。家康は北条時代の堀を埋めて本丸を拡張していった
おわかりだろうか? 神君家康公は、自分のことより家臣の暮らしが立つことを優先する、家臣思いのありがたい殿様だった、といっているのだ。現代の独裁国家で指導者様を讃えるために語られるエピソードと、基本は同じでなのある。そうした国では人民が飢えや戦争に苦しんでいても、指導者様は福々しいお姿をしているではないか。
『徳川実紀』が伝えるボロ城エピソードを、額面どおりに受け取ったら、われわれは『実紀』編者の術中に落ちることになる。では、実態はどう考えればよいのだろうか。
 八王子城御主殿では発掘調査で豪壮な御殿の礎石が確認されている。江戸城の本丸にもこのような御殿が建っていただろう
八王子城御主殿では発掘調査で豪壮な御殿の礎石が確認されている。江戸城の本丸にもこのような御殿が建っていただろう
まず、踏まえておくべきは、家康の入った江戸城が敗残の城だったことだ。小田原の役に際して、北条軍は小田原城に精鋭部隊を集結させて、各地の城は留守居の将と近在から徴収した民兵によって守備させる方針を採っていた。
江戸城も同様だっはずで、大量の民兵を収容した状態で敵軍を迎え、投降開城したのだから、城内はかなり荒廃しただろう。城下の主要部分も焼失していた可能性が高い。住民の中にも、戦火を避けて疎開した者が多かっただろう。
しかも、徳川軍が江戸城を接収したのは4月末で、家康が入ったのが8月1日。この間、徳川軍の主力は岩付や房総などを転戦しているから、江戸城に駐留していたのは、警備と中継任務にある少人数の城番だけだろう。
 江戸城本丸の汐見坂。家康の頃にはここから日比谷入江の海面が見えたという
江戸城本丸の汐見坂。家康の頃にはここから日比谷入江の海面が見えたという
つまり、江戸の城と城下は、敗残の状態で夏場の3ヶ月を送っていたのだ。城内も城下も草ぼーぼーの荒れ放題だったのは、当然なのである。家康と三河武士たちり込んできたのは、そんな状態の江戸だったのだ。
彼らの間でどんな話が語り継がれたかは、想像に難くない。
「家康公が入った頃の江戸はひどかったよなあ」
「俺の屋敷のまわもり原っぱだったからなあ」
といった思い出話・苦労話の鉄板ネタに、「家康公は家臣思いのありがたい殿様だった」というプロパガンダが乗っかる。かくて神君家康公の江戸創業神話ができあがる、というわけだ。
 西ノ丸下(皇居外苑)から見た丸ノ内のビル群。家康が入った頃は丸ノ内あたりまで入江が入り込んでいた
西ノ丸下(皇居外苑)から見た丸ノ内のビル群。家康が入った頃は丸ノ内あたりまで入江が入り込んでいた
家康が入った頃の江戸は寒村で城もボロだったというエピソードは、江戸東京の都市伝説第1号といってよいかもしれない。
 江戸城の桜田濠。「寒村ボロ城」は江戸東京の都市伝説か
江戸城の桜田濠。「寒村ボロ城」は江戸東京の都市伝説か
[お知らせ]発売中の『歴史群像』10月号に、家康入城時の姿に迫る拙稿「武蔵・江戸城」が掲載されています。筆者の考証に基づいて香川元太郎氏が描いた江戸城の想像イラストは、まさに家康の入城シーンを再現したもの。ぜひ、ご一読下さい!